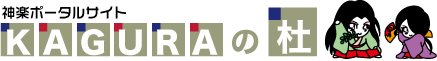■神楽団・社中検索
▼三次市
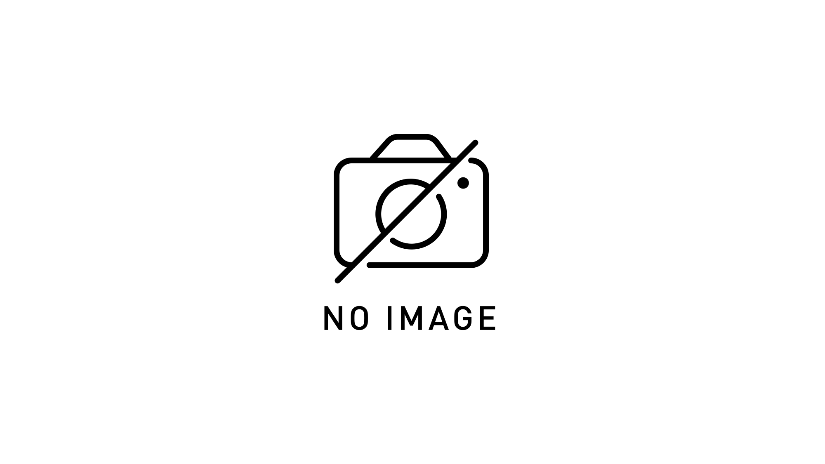
伊賀和志神楽団
〒728-0111
広島県三次市作木町伊賀和志
代表者(団長):三上 広隆
詳細はこちら
【氏神神社名】伊賀和志天満宮社【団体の発足時期】300~600年前
【伝承されている神楽の区分】石見神楽の内、邑智神楽の阿須那派
【保持演目】<旧舞>鈴合せ(県無形民俗文化財)、神降ろし(市無形民俗文化財)、天の岩戸(市無形民俗文化財)、悪切、恵比須、八幡、鍾馗、塵倫、天神、大江山、山伏、田村、みさき、八岐大蛇、山の大王、貴船、鞨鼓切目、胴の口など
<新舞>悪狐伝、戻り橋、葛城山、小掛山
【備考】伊賀和志神楽は、石見神楽のうち邑智33神楽の阿須那派に属しています。
起源は定かではありませんが、遠く源平の時代、平家の落武者達が在りし日の都の生活を偲びつつ舞い、唄い伝え伝えて何時のころよりか、邑智33神楽のひとつとなって舞い伝えられてきたと云われています。
約600年前、石見地方より移入せられたもので、石見神楽の内邑智系33神楽に属するもので、代々土地の有志により伝承せられ今日に及んだものである
。中でも「天の岩戸」及び「鈴合せ」の舞は古来の出雲神楽の古式をそのまま伝承したもので、最も尊ばれている。
【更新日】2006/5/3
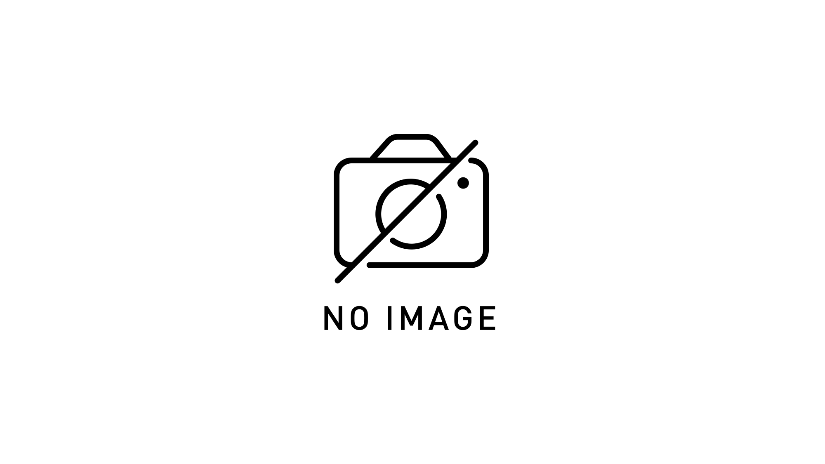
横谷神楽団
〒728-0024
広島県三次市青河町
代表者(団長):通地 翼
詳細はこちら
【氏神神社名】---【団体の発足時期】昭和60年4月
【伝承されている神楽の区分】石見神楽(八調子高田舞)
【保持演目】<旧舞>神迎え・鍾馗・八幡・塵倫・日本武尊・八岐大蛇・恵比寿
<新舞>悪狐伝(中編)・土蜘蛛・滝夜叉姫・紅葉狩・羅生門・大江山・山姥・源頼政・稲生平太郎(比熊山)
【備考】私たち横谷神楽団は、横谷地区壮青年の神楽愛好者が昭和55年の横谷小学校校歌開き行事での神楽発表を契機に、素人の域ながら太鼓を打ち、心はずませて夜の更けるのも忘れて語り合ううちに、昭和58年に横谷神楽クラブとして組織的な活動を始めました。以後、地域の皆様方のご支援を受けながら各地での公演を行っていました。
その後、この活動を更に発展させるため、昭和60年「横谷の神楽として、子や孫に自信を持って伝承できる神楽団づくり」を目標に20名の団員で神楽団としての活動を開始しました。各地のお祭りや、神楽大会、イベントなどの他、病院などの慰問や結婚式など年間20回から40回の公演を重ね、東京都や愛知県、山口県など県外の神社でも奉納をさせていただきました。
また、平成2年からは、横谷小学校神楽クラブ(平成18年4月から横谷子ども神楽クラブ)への指導もしています。
現在は、20代から60代までの28名の団員で日々精進しています。
【更新日】2006/5/4
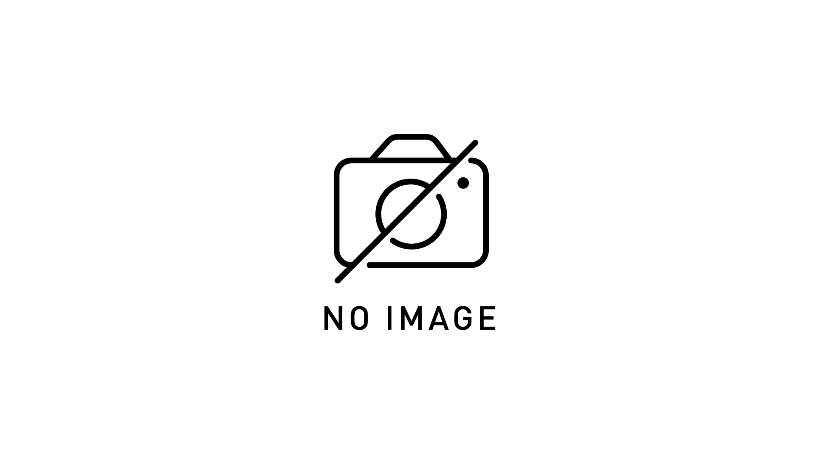
布野神楽団
〒728-0202
広島県三次市布野町下布野
代表者(団長):品川 則博
詳細はこちら
【氏神神社名】知波夜比売神社【団体の発足時期】明治初期
【伝承されている神楽の区分】石見神楽の中の邑智神楽 阿須那派
【保持演目】
<旧舞>神降ろし,八幡,鍾馗,天神,天の岩戸,恵比寿,塵倫,八岐大蛇,山伏,大江山など
<新舞>葛城山(布野神楽団独自の山賊退治) 【備考】布野神楽団は,邑智神楽の阿須那派に所属しています。
地元神楽に旧くより,神宮により引き継がれていたものが,氏子の手に委ねられ神楽組が結成されました。 これが,布野神楽団発足の基となったものです。
毎年,地元神社では,宇津女の命が祀られているため,「天の岩戸」を奉納するとともに,合わせて皆様方の五穀豊穣,無病息災を祈願して「鍾馗」を奉納しています。。
【更新日】2015.5.6
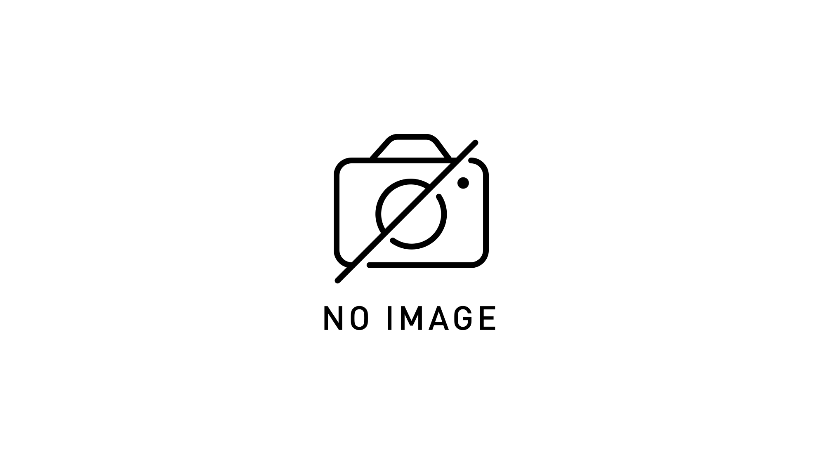
甲奴神楽同好会
〒729-4102
広島県三次市甲奴町西野
代表者(団長):下宮 昌三
詳細はこちら
【氏神神社名】須佐神社・本郷八幡神社・西野西山八幡神社【団体の発足時期】昭和42年2月
【伝承されている神楽の区分】三谿(みたに)系備後神楽
【保持演目】神事 (能)八重垣、恵比寿(特技演目)
【備考】甲奴神楽は古く三谿系備後神楽の流れを継承の為、同好の士相集い10名にて発足、現在に至る。
【更新日】2006/5/1
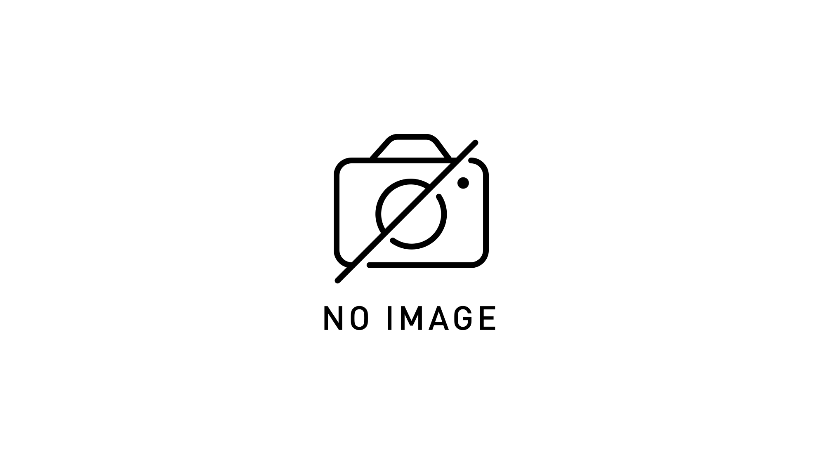
穴笠神楽団
〒728-0004
広島県三次市穴笠町
代表者(団長):神田 幸雄
詳細はこちら
【氏神神社名】天津神社【団体の発足時期】昭和60年4月
【伝承されている神楽の区分】阿須那系 梶矢神楽
【保持演目】
<新舞>神降し・塵倫・羅生門・伊吹山・滝夜叉姫・葛城山・大江山・信州戸隠山・熊襲征伐・恵比寿舞・山姥・鈴鹿山・源頼政・八岐大蛇
<穴笠オリジナル>将門の乱・明神山
【備考】穴笠神楽団発足のきっかけは、1985年、三次市穴笠町の地元青年団が町興しとして神楽を始めたことによる。梶矢神楽団からの指導のもと練習を重ねた。
3年後の1988年天津神社に初めて神楽を奉納し、地元の声援を受け、翌年1989年穴笠青年団から穴笠神楽同好会に名称を変更し、週一度の練習を続けながら、地元ふれあい祭り・地域敬老会等への出演を続けてきた。
平成16年10月穴笠神楽団と名称を変更し、同時に子ども神楽団も結成し、現在に至る。 【更新日】2006/5/2
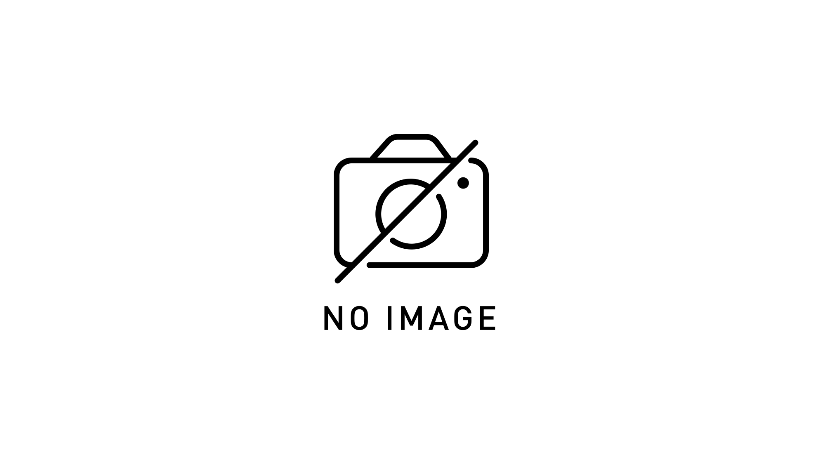
茂田神楽団
〒728-0403
広島県三次市君田藤兼
代表者(団長):岸本 正行
詳細はこちら
【氏神神社名】---【団体の発足時期】---
【伝承されている神楽の区分】---
【保持演目】神降し・天の岩戸・恵比須・山伏・塵倫・八幡・八岐大蛇・大江山・葛城山・山姥・日本武尊・戻り橋・滝夜叉姫
【備考】君田町茂田地区では、約180年以前、出雲・石見地方より神楽を習い、茂田神楽団として伝承されてきました。当時、砂鉄採取が盛んに行なわれ、砂鉄労働者の安全祈願と農家の五穀豊穣を願い、毎年秋祭りに奉納されてきました。地区の団員不足により昭和54年に旧君田村全体に呼びかけ、君田村茂田神楽団として再結成され、市町村合併後は茂田神楽団として、君田温泉森の泉公演、各地の共演大会、各種イベント、秋祭りなどに出演しています。
【更新日】2006.5.20