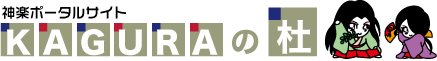■神楽団・社中検索
▼浜田市
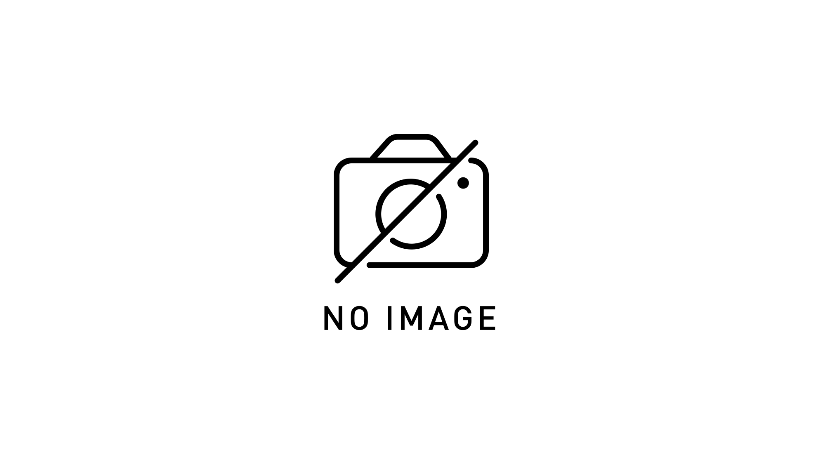
岡崎神楽社中
〒699-3211
島根県浜田市三隅町三隅
代表者:吉本 明正
詳細はこちら
【氏神神社名】三角神社【団体の発足時期】江戸時代
【伝承されている神楽の区分】石見神楽 八調子
【保持演目】
<旧舞>楽・塩祓・八幡・天神・塵輪・道がへし・黒塚・鐘馗・恵比須・岩戸・貴船・頼政・かっこ・切目・日本武尊・大蛇
<新舞>弁慶・大江山 【備考】江戸時代より発足 石見神楽の中でも最も古い社中とされている 八調子神楽
【更新日】 2006/5/2
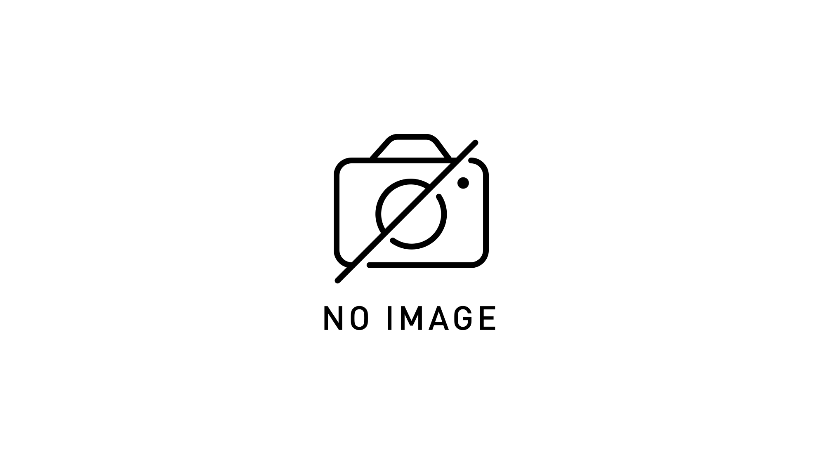
岡見神遊座
〒699-3226
島根県浜田市三隅町岡見
代表者:齋藤 鉄也
詳細はこちら
【氏神神社名】---【団体の発足時期】---
【伝承されている神楽の区分】---
【保持演目】
鈴神楽・塩祓い・神迎え・恵比須・黒塚・五神・鐘馗・塵輪・道がえし・天神・八幡・大蛇・日本武尊・鈴鹿山・岩見重太郎・十羅刹女・大江山・かっ鼓・切目
【備考】---
【更新日】---
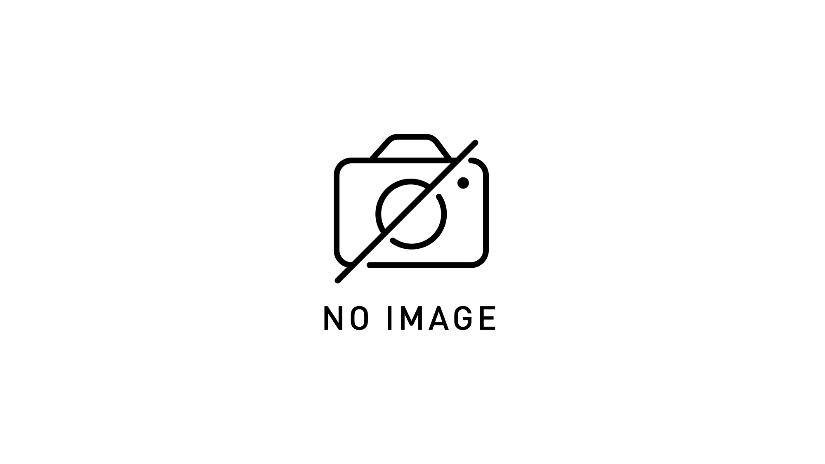
石見神楽 松原神楽社中
〒699-3226
島根県浜田市三隅町岡見松原
代表者: 野上 尚雄
詳細はこちら
【氏神神社名】愛宕神社【団体の発足時期】昭和55年
【伝承されている神楽の区分】石見神楽
【保持演目】神楽・塩祓・四剣・八幡・天神・恵比須・塵輪・黒塚・かっ鼓 切目・頼政・十羅刹女・鐘馗・鈴ヶ山・石神(いわがみ)・八衢・岩戸・鬼返し・八岐大蛇
【備考】石見神楽の古きよきのもと新しい時代のニーズにあった神楽社中を目指そうと、三隅町松原地区の若者を中心に昭和55年に社中を結成。以来、地区の愛宕神社の夏、秋の例祭はじめ、町内はもとより中国地方の奉納神楽や神楽大会に出場すると共に、各地域のイベントに多数参加させていただいております。
迫力ある囃子、躍動感あふれる舞をモットーに、1人でも多くの人に石見神楽の良さを知ってもらい、心に残る感動のある神楽をと、社中員一同、 日々練習をかさねております。今後とも温かいご声援、ご指導の程、よろしくお願いいたします。
【更新日】2006/5/1
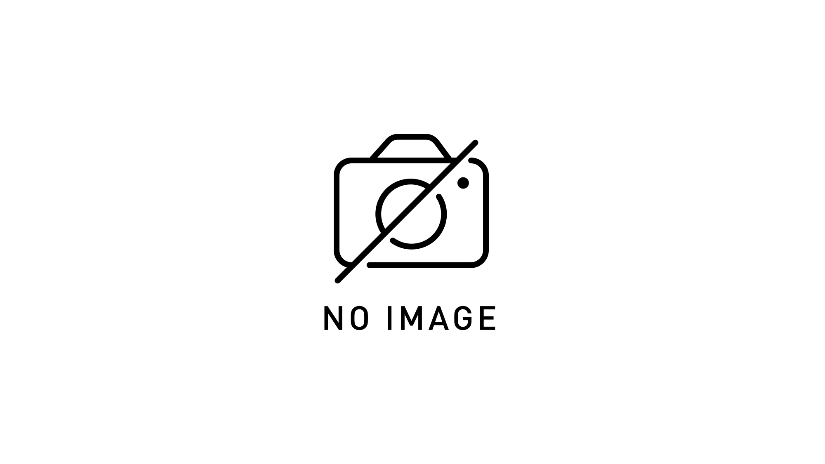
河内奏楽中
〒699-3215
島根県浜田市三隅町下古和
代表者:三浦 幸人
詳細はこちら
【氏神神社名】河内八幡宮【団体の発足時期】明治初期
【伝承されている神楽の区分】石見神楽
【保持演目】<旧舞>五神・鐘馗 など約20演目
<新舞>三隅兼連
【備考】明治初年頃に、近隣の寺社の為の奉楽連として発足しました。当初は奏楽(雅楽)演奏のみでしたが、神楽が伝授され、現在は神楽主体で活躍しています。
「奏楽中」の名称は、伊勢神宮により授与されたと伝えられています。
【更新日】2006/5/16

両谷神楽社中
〒699-3301
島根県浜田市三隅町大字井野
代表者:杉本 勝則
詳細はこちら
【氏神神社名】---【団体の発足時期】---
【伝承されている神楽の区分】---
【保持演目】
恵比須・黒塚・鍾馗・塵輪・道がえし・天神・八幡・八十神・大蛇・日本武尊
【備考】---
【更新日】---
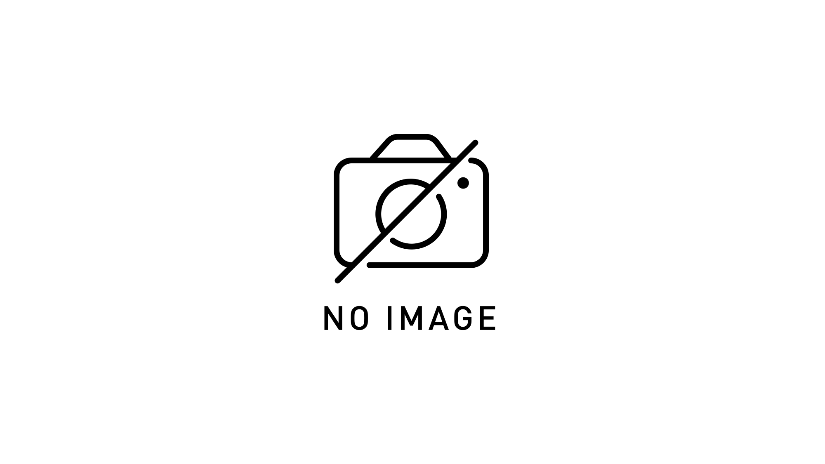
井野神楽
〒699-3301
島根県浜田市三隅町井野
代表者:串崎 紀典
詳細はこちら
【氏神神社名】---【団体の発足時期】---
【伝承されている神楽の区分】---
【保持演目】
神楽・塩祓い・神迎え・神祇太鼓・帯舞・四神・四剣・御座・五穀種元・俵舞・真榊・湯立・岩戸・恵比須・鹿島・かっ鼓・切目・貴船・熊襲・黒塚・五神・鐘馗・神武・塵輪・道がえし・天神・八幡・八衢・八十神・大蛇・日本武尊・頼政・大江山・伊佐那岐・海幸山幸・朝雄・武ノ内
【備考】島根県指定無形民俗文化財
【更新日】---
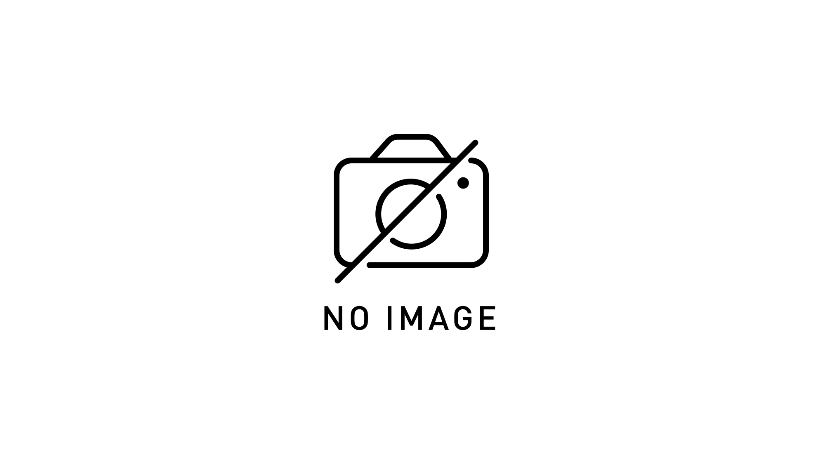
安城神楽社中
〒697-1215
島根県浜田市弥栄町稲代
代表者:小松原 茂
詳細はこちら
【氏神神社名】長安八幡宮【団体の発足時期】文久元年(1861)
【伝承されている神楽の区分】石見神楽
【保持演目】
塩祓い・神迎え・帯舞・真榊・岩戸・恵比須・かっ鼓・切目・黒塚・五神・鐘馗・塵輪・道がえし・天神・八幡・八衢・八十神・大蛇・日本武尊
【備考】
安城神楽社中は、文久元年(1861)に始められたと伝えられ、140余年の長きにわたり多くの先輩達によって伝承されてきました。明治中期までは神職中心の神楽で六調子で演じられていたようです。その後、一般氏子で演じられるようになり、石見神楽独特の八調子で演ずるようになりました。現在19名のメンバーで構成しており、国内外各地の祭り、イベントなどに積極的に参加しております。
先人達が血のにじむような思いで残してくれた貴重な郷土芸能を正しく後世に伝承すべく努力をしております。
【更新日】2006/5/2
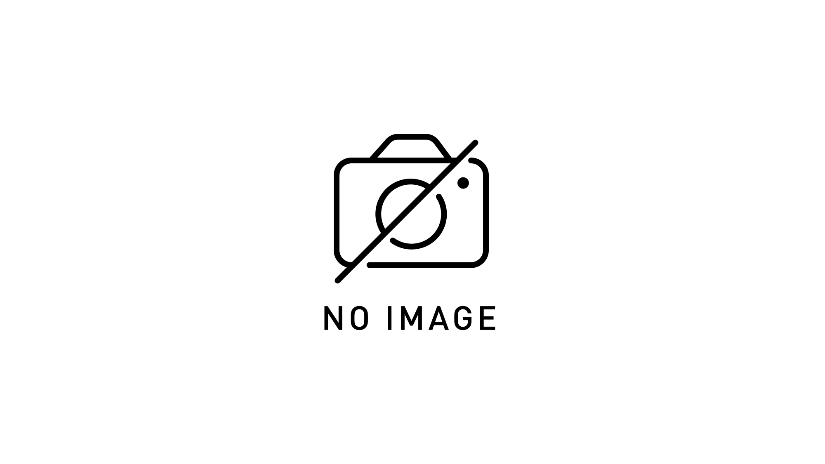
杵束神楽社中
〒697-1122
島根県浜田市弥栄町木都賀
代表者:河上 茂
詳細はこちら
【氏神神社名】---【団体の発足時期】---
【伝承されている神楽の区分】---
【保持演目】
黒塚・大蛇・道がえし・岩戸・五神・鍾馗・塵輪・八幡・八衢
【備考】---
【更新日】2006/2/7
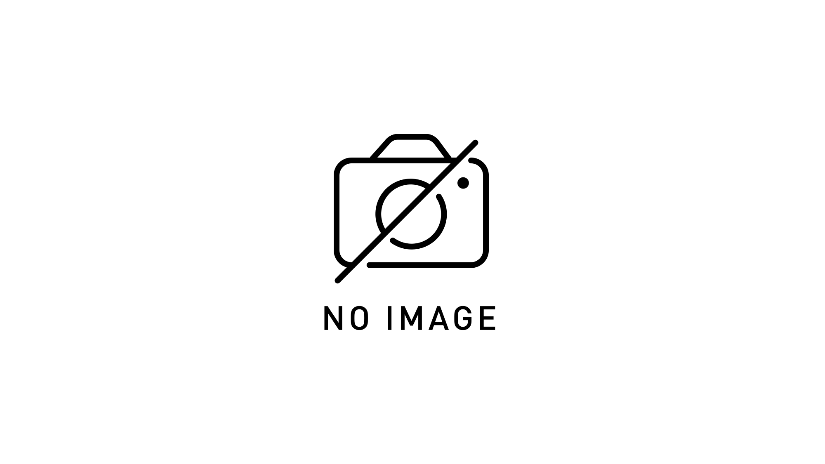
市木神社神楽団
〒697-0514
島根県浜田市旭町市木
代表者:槇野 秀雄
詳細はこちら
【氏神神社名】市木神社【団体の発足時期】---
【伝承されている神楽の区分】石見神楽 六調子
【保持演目】
<旧舞>神迎・潮祓・岩戸・剣舞・塵輪・切目・鈴合・神武・宇佐・杵桶・鐘馗・恵美須・鈴ヶ山・貴船・天神・八咫・黒塚・五龍王
【備考】石見神楽の六調子
【更新日】2006/2/7
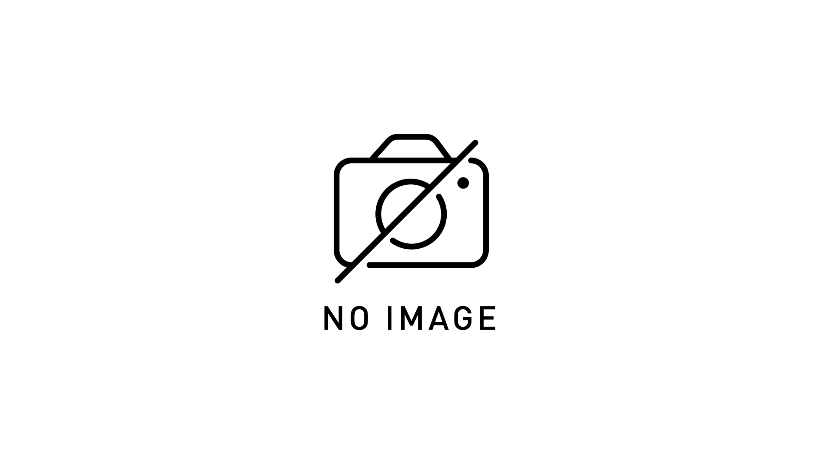
今市神楽社中
〒697-0425
島根県浜田市旭町今市
代表者:服部 征洋
詳細はこちら
【氏神神社名】---【団体の発足時期】---
【伝承されている神楽の区分】---
【保持演目】
神降し・神迎え・岩戸・恵比須・大江山・黒塚・鐘馗・神武・塵輪・天神・八幡・八岐大蛇・岩見重太郎ひひ退治・紅葉狩
【備考】---
【更新日2006/2/7
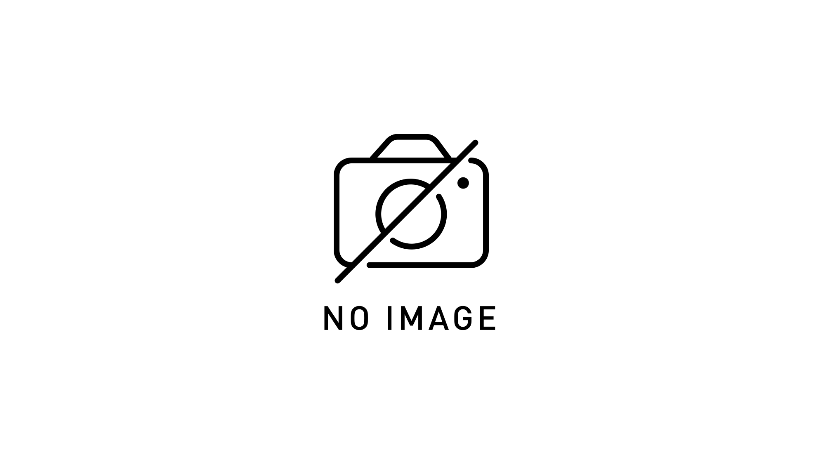
木田神楽社中
〒697-0427
島根県浜田市旭町木田
代表者:山崎 英俊
詳細はこちら
【氏神神社名】---【団体の発足時期】---
【伝承されている神楽の区分】---
【保持演目】
神迎え・鍾馗・塵輪・天神・大蛇・鈴鹿山
【備考】---
【更新日】---
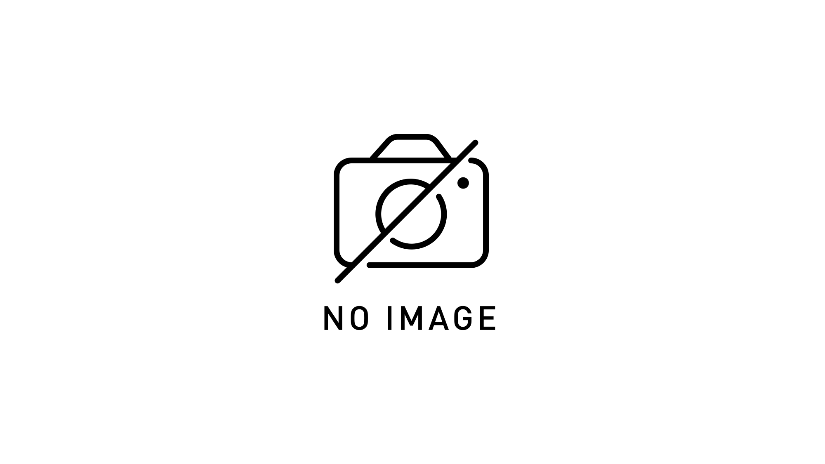
坂本神楽社中
〒697-0431
島根県浜田市旭町坂本
代表者:大屋 初幸
詳細はこちら
【氏神神社名】---【団体の発足時期】---
【伝承されている神楽の区分】---
【保持演目】---
【備考】---
【更新日】---
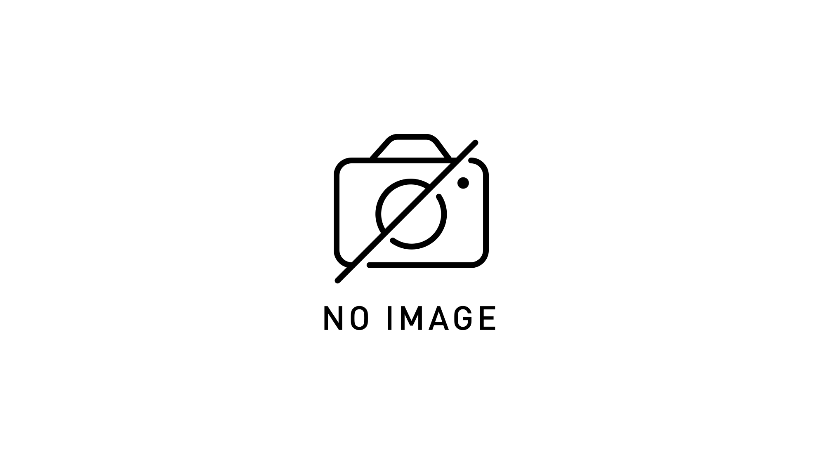
重富神楽社中
〒697-0423
島根県浜田市旭町重富
代表者:山崎 勝幸
詳細はこちら
【氏神神社名】---【団体の発足時期】---
【伝承されている神楽の区分】---
【保持演目】
神降し・神迎え・神祇太鼓・天蓋・磐戸・恵比須・鐘馗・神武・塵輪・天神・八幡・八岐大蛇・鈴鹿山・大江山
【備考】重富神楽社中は、重富八幡宮にて明治初期まで神事に併せて神職により神楽舞が奉納された様ですが、その頃より神職の手伝い役として氏子が加勢して演ずるようになりこれ以後重富神楽社中として発足し、神楽は地区民の慰安楽しみとして盛大に奉納されるようになり現在は郷土芸能として、また地区の活性化の一端として継承されております。
【更新日】2006/2/7
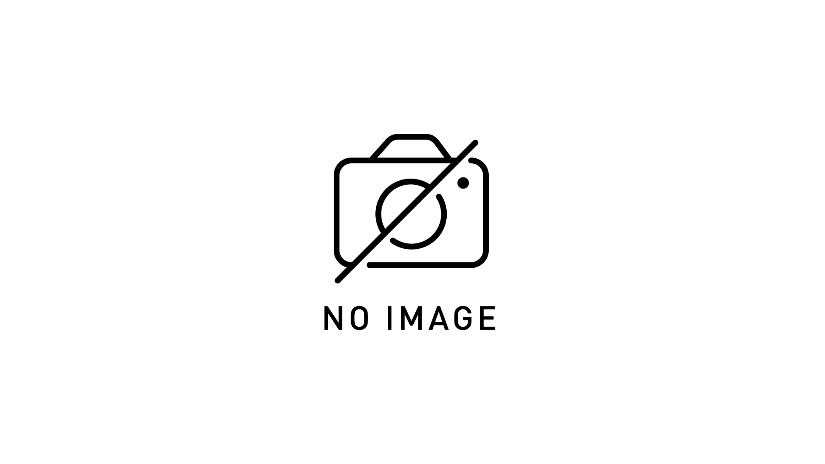
石見神楽 都川神楽団
〒697-0511
島根県浜田市旭町都川
代表者:安床 俊雄
詳細はこちら
【氏神神社名】---【団体の発足時期】---
【伝承されている神楽の区分】---
【保持演目】
塩祓い・神迎え・神祇太鼓・剣舞・四剣・岩戸・恵比須・大江山・熊襲・黒塚・五龍王・鐘馗・神武・塵輪・天神・八幡・八岐大蛇・八神姫・五条橋
【備考】---
【更新日】2006/2/7
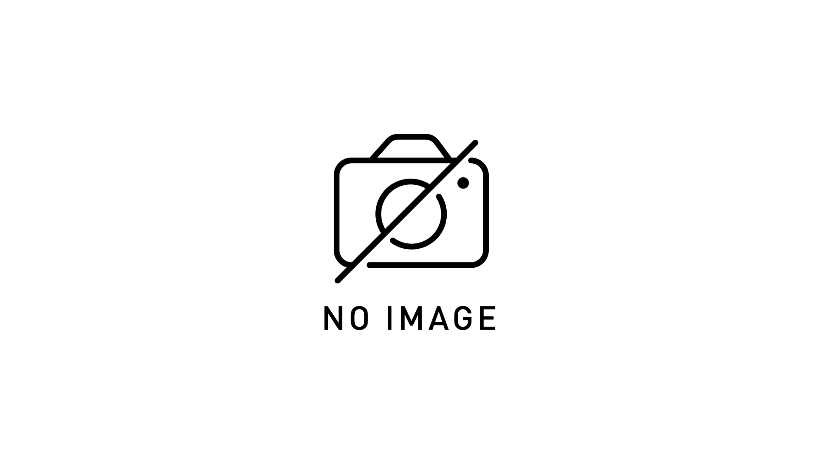
本郷神楽社中
〒697-0422
島根県浜田市旭町本郷
代表者:岩谷 欣吾
詳細はこちら
【氏神神社名】---【団体の発足時期】---
【伝承されている神楽の区分】---
【保持演目】
神迎え・岩戸・恵比須・かっ鼓・切目・鐘馗・神武・天神・弓八幡・大蛇・神武・鈴鹿山・大江山・牛若丸
【備考】---
【更新日】2006.2.7
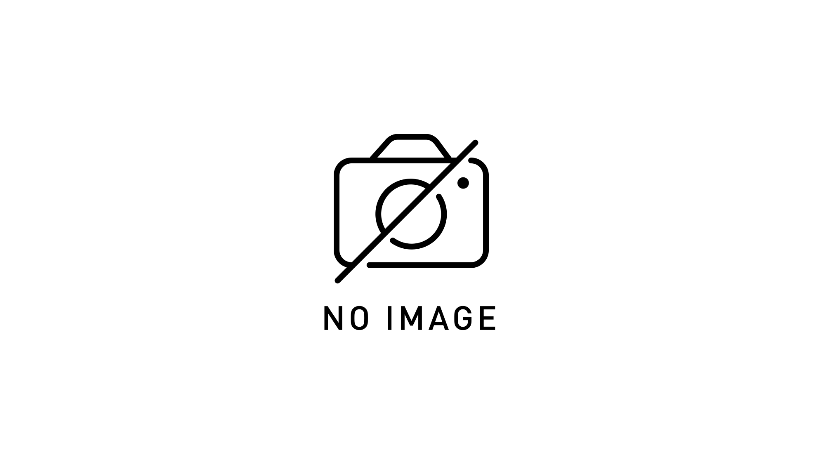
来尾神楽団
〒697-0512
島根県浜田市旭町来尾
代表者:市川 清志
詳細はこちら
【氏神神社名】来尾神社【団体の発足時期】明治時代
【伝承されている神楽の区分】石見神楽
【保持演目】
<旧舞>神迎・塩祓・岩戸・神輪・神武・鐘馗・大蛇・八幡・天神・四剣・恵比須
<新舞>滝夜叉姫・土蜘蛛
【備考】明治中期に発足したが、昭和30~40年代頃、人員不足により廃団の危機に立たされたが、女性の方(3~4人)に協力をいただき継続することができ、現在に至る。
聞くところによると、神楽の流れは芸北の神楽によるところがおおく、調子は六調子と八調子の中間ぐらい。
【更新日】2006/5/2
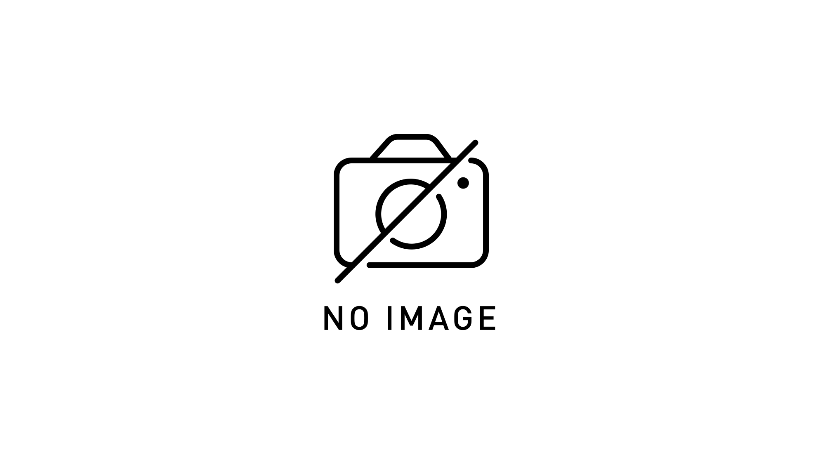
和田神楽社中
〒697-0424
島根県浜田市旭町和田
代表者:長山 一夫
詳細はこちら
【氏神神社名】---【団体の発足時期】---
【伝承されている神楽の区分】---
【保持演目】
恵比須・鍾馗・塵輪・八幡・神武
【備考】---
【更新日】---
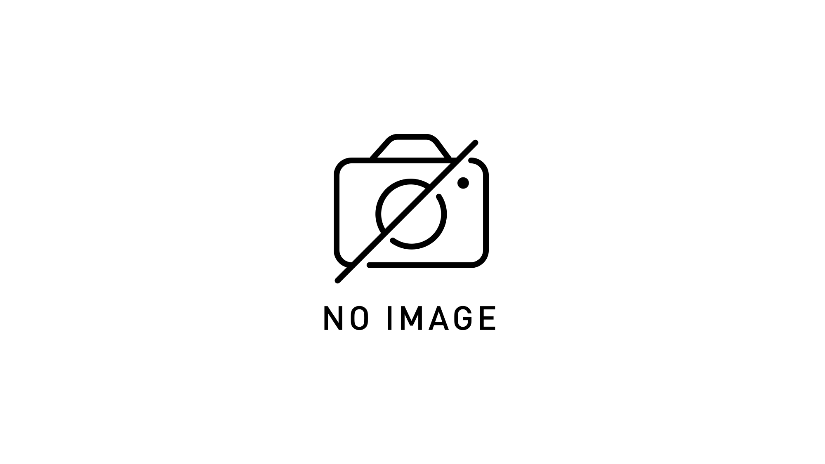
丸原神楽社中
〒697-0426
島根県浜田市旭町高杉谷
代表者:大屋 三千年
詳細はこちら
【氏神神社名】---【団体の発足時期】---
【伝承されている神楽の区分】石見神楽 打切八調子
【保持演目】
塩祓い・黒塚・塵輪・天神・大蛇・八幡・恵比須・道がえし・頼政・鍾馗・神武東征
【備考】---
【更新日】---
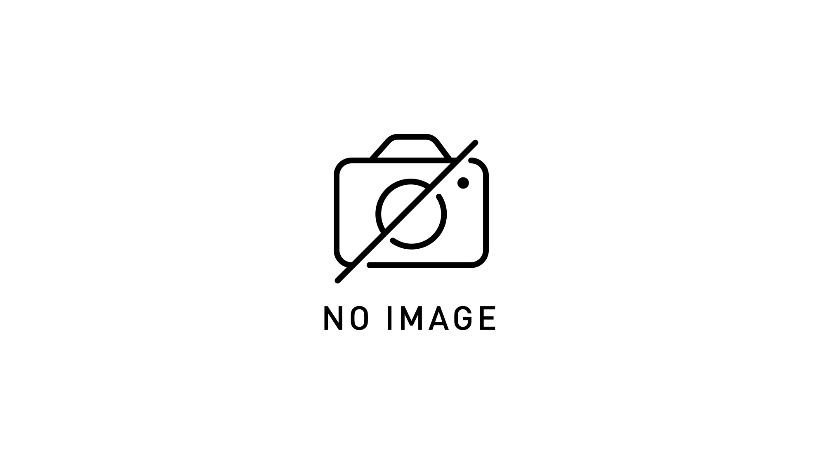
小笹神楽社中
〒697-0123
島根県浜田市金城町七条
代表者:梅岡 篤人
詳細はこちら
【氏神神社名】---【団体の発足時期】---
【伝承されている神楽の区分】---
【保持演目】
鈴神楽・塩祓い・神迎え・神祇太鼓・四神・五穀種元・岩戸・恵比須・鹿島・かっ鼓・切目・黒塚・五神・鐘馗・塵輪・道がえし・天神・八幡・八衢・八十神・大蛇・日本武尊
【備考】---
【更新日】2006/2/7
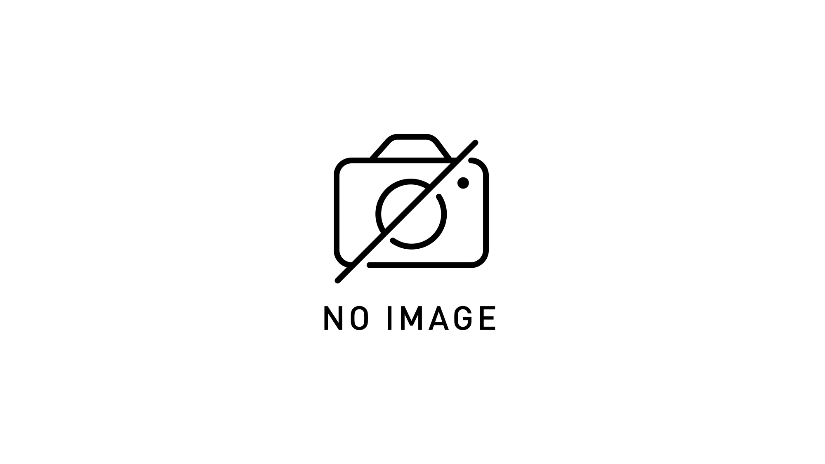
若林神楽社中
〒697-0123
島根県浜田市金城町七条
代表者:田村 浩三
詳細はこちら
【氏神神社名】---【団体の発足時期】---
【伝承されている神楽の区分】---
【保持演目】
塩祓い・恵比須・鹿島・黒塚・鍾馗・塵輪・天神・八十神・大蛇・五神
【備考】---
【更新日】---
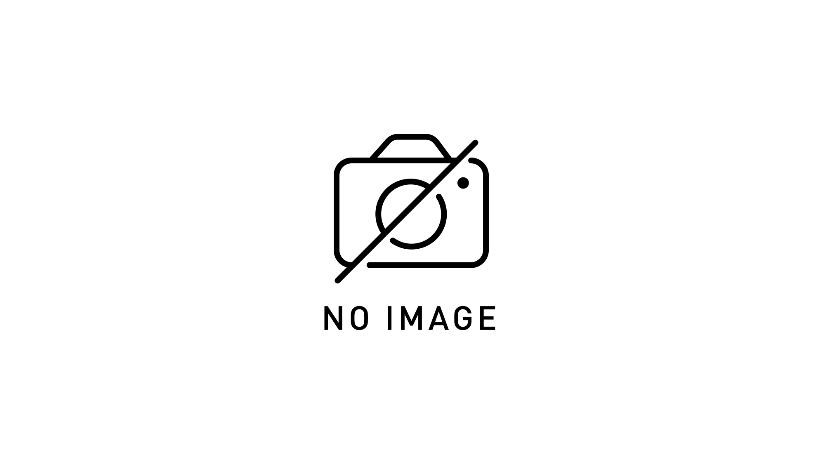
伊木神楽社中
〒697-0123
島根県浜田市金城町七条伊木
代表者:山本 泰介
詳細はこちら
【氏神神社名】猪伏山八幡宮【団体の発足時期】明治20年
【伝承されている神楽の区分】石見神楽
【保持演目】
<旧舞>神楽・塩祓・神迎・八幡・神祇太鼓・かっ鼓・切り目・四神・鹿島・塵輪・八十神・天神・黒塚・鐘馗・日本武尊・岩戸・恵比須・大蛇・五穀種元・頼政・五神
【備考】
現在、伊木の里に伝わる八調子の神楽は明治20年代の終わり頃、渡辺五郎、山東梅吉の2人の先駆者が習い伝えたと言われる。以後、大正・昭和期と隆盛期が続いたが、若年層の流出で人手不足により活動を中断し、この里から神楽が消滅した。しかし、Uターン現象により昭和49年に復活、現在に至っている。古式に則った神楽の演舞に心がけるよう、社中一同、申し合わせている。
【更新日】 2006/5/2

上来原神楽社中
〒697-0122
島根県浜田市金城町上来原
代表者:岡本 則幸
詳細はこちら
【氏神神社名】---【団体の発足時期】---
【伝承されている神楽の区分】---
【保持演目】
鈴神楽・貴船・帯舞・塵輪・天神・頼政・大蛇・鐘馗
【備考】---
【更新日】---
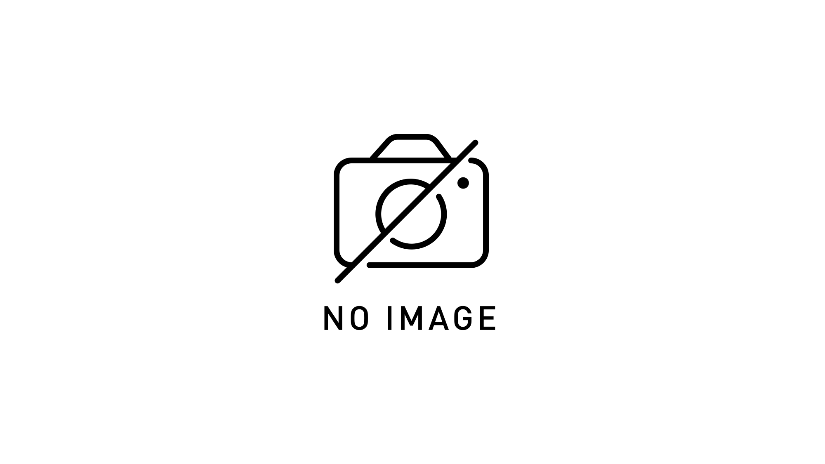
下来原西組神楽社中
〒697-0121
島根県浜田市金城町下来原
代表者:宇川 健
詳細はこちら
【氏神神社名】---【団体の発足時期】---
【伝承されている神楽の区分】---
【保持演目】
塩祓い・四神・恵比須・かっ鼓・切目・黒塚・鐘馗・塵輪・道がえし・八幡・八十神・大蛇・日本武尊・岩戸・頼政
【備考】---
【更新日】---
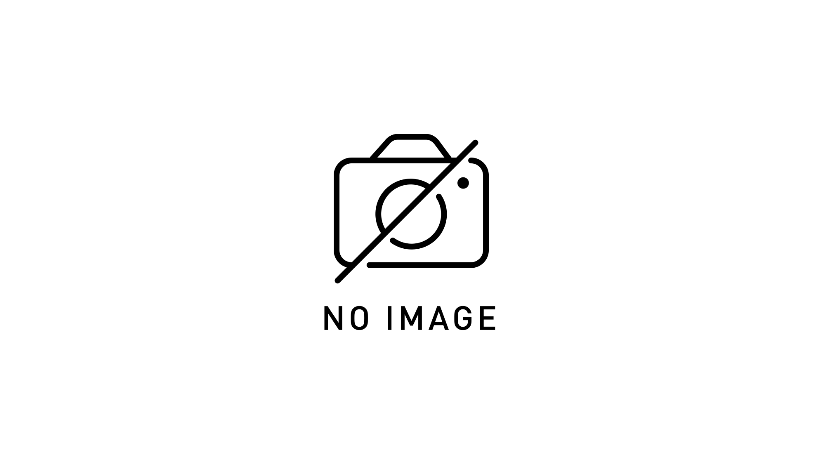
久佐西組神楽社中
〒697-0303
島根県浜田市金城町久佐
代表者:小谷 保雄
詳細はこちら
【氏神神社名】---【団体の発足時期】---
【伝承されている神楽の区分】---
【保持演目】
鈴神楽・塩祓い・恵比須・かっ鼓・鐘馗・塵輪・道がえし・天神・大蛇・頼政・牛若丸・大江山・八十神・鹿島・黒塚
【備考】---
【更新日】---
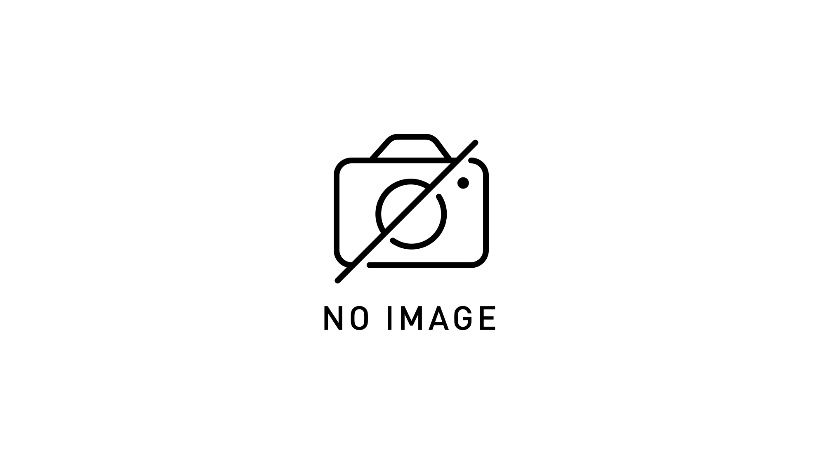
久佐東神楽社中
〒697-0303
島根県浜田市金城町久佐
代表者:岡本 孝宏
詳細はこちら
【氏神神社名】---【団体の発足時期】---
【伝承されている神楽の区分】---
【保持演目】
塩祓い・四神・尊神・恵比須・熊襲・黒塚・鐘馗・神武・塵輪・道がえし・天神・八幡・八十神・大蛇・頼政・大江山
【備考】
神官によって舞われていた神職神楽が明治の初期に発令されたが、神職演舞禁止令により、久佐八幡宮神官であった「山崎義任氏」によって氏子若連中に引き継がれ、久佐舞子連中として六調子神楽が発足した。
時期は判明しないが言い伝えによると、明治12年以前とされていて、黒地に真赤な朝日が昇る平幕に明治12年と書かれていたとのこと。また、今でも木彫の面や古い衣装も数多く保存している。
大正に入って、久佐上地区に八調子神楽が伝えられたため、久佐下地区が六調子神楽を継承し、久佐東神楽社中として現在に至っている。
【更新日】---
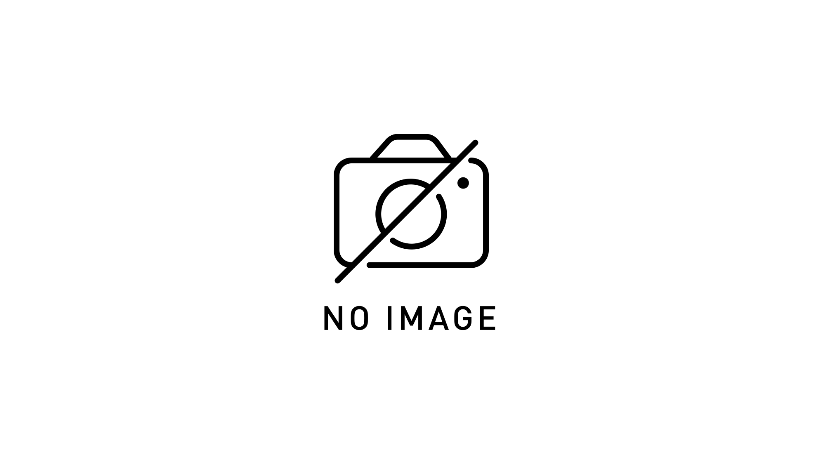
小国神楽社中
〒697-0123
島根県浜田市金城町小国
代表者:山本 幸雄
詳細はこちら
【氏神神社名】---【団体の発足時期】---
【伝承されている神楽の区分】---
【保持演目】---
【備考】---
【更新日】---
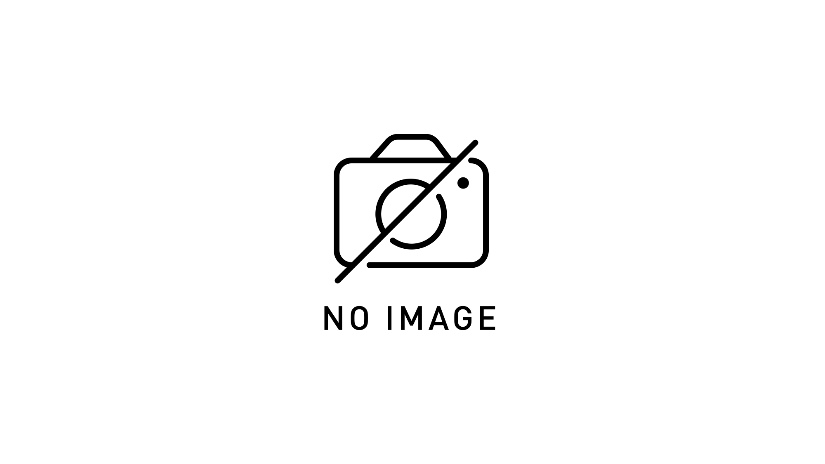
柚根神楽社中
〒697-0213
島根県浜田市金城町小国
代表者:山岡 憲真
詳細はこちら
【氏神神社名】---【団体の発足時期】---
【伝承されている神楽の区分】---
【保持演目】---
【備考】---
【更新日】---
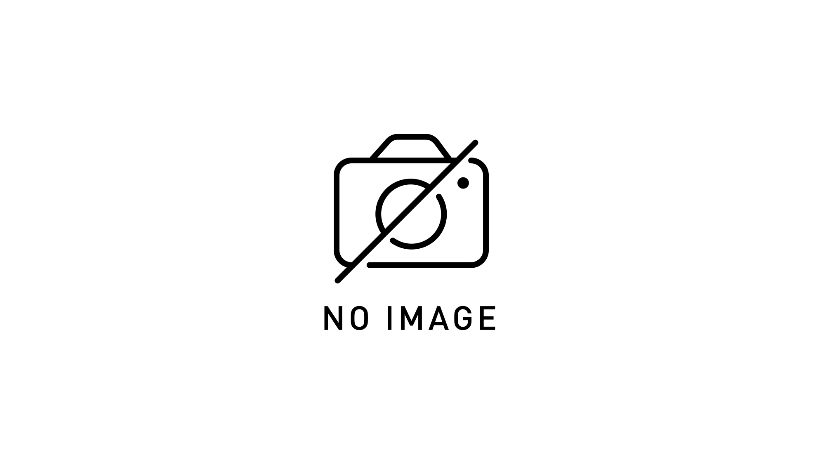
石見神楽 今福神楽社中
〒697-0305
島根県浜田市金城町入野
代表者:河上 竜彦
詳細はこちら
【氏神神社名】今福八幡宮【団体の発足時期】明治初期
【伝承されている神楽の区分】石見神楽
【保持演目】
<旧舞>神楽・塩祓・御座・八幡・かっ鼓・切目・道がえし・四神・鹿島・天蓋・塵輪・天神・黒塚・鐘馗・日本武尊・神武・恵比須・大蛇・頼政・八衢
<新舞>紅葉狩・滝夜叉姫
【備考】
今福神楽社中は六調子から八調子に移行したのは、明治初期、郷社今福八幡宮に奉納されていた神職神楽を里神楽として皆合地区の若者が「皆合の舞子連中」として受け継ぎ昭和8年に浜田市長見神楽社中(藤川氏)より八調子神楽を習得したが、第二次世界大戦に舞子の若者が出兵し、神楽の演目によっては舞い姿がわからなくなり昭和21年に浜田市長浜社中(坂本氏)より新たに八調子神楽を習得したと聞いている。一時期後継者不足でしたが地域の輪を広げ、美又地区や雲城地区からも活動に参加していただき昭和45年に今福神楽社中として再結成し、現在では女性団員も社中の大黒柱として一緒になって、新しい神楽にも挑戦しながら保存伝承に取り組んでいる。
社中は、同好会的な組織ではなく、長年、神社とともに歩んできた社中だり、氏子の方々も神楽に対して協力的で、町内の催事はもちろん、県内外の各種神楽大会や行事に招かれ、優勝、準優勝などをしている。最近では平成13年かなぎ競演大会に優勝した実績があり、県外の神楽競演大会にも出場して地元神楽団体との交流も行い、町のPRや都市と山村の交流にも役立っている。
【更新日】2006/5/2
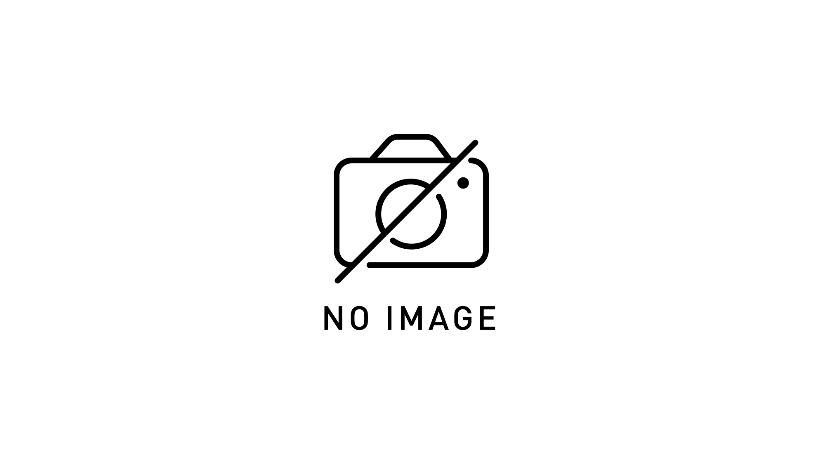
波佐常磐倶楽部
〒697-0212
島根県浜田市金城町
代表者:岡本 謙二
詳細はこちら
【氏神神社名】---【団体の発足時期】---
【伝承されている神楽の区分】---
【保持演目】
四方祓・四神・四剣・尊神・天蓋・岩戸・恵比須・大江山・黒塚・鐘馗・神武・塵輪・道がえし・天神・八幡・大蛇・頼政
【備考】---
【更新日】 2006/2/7
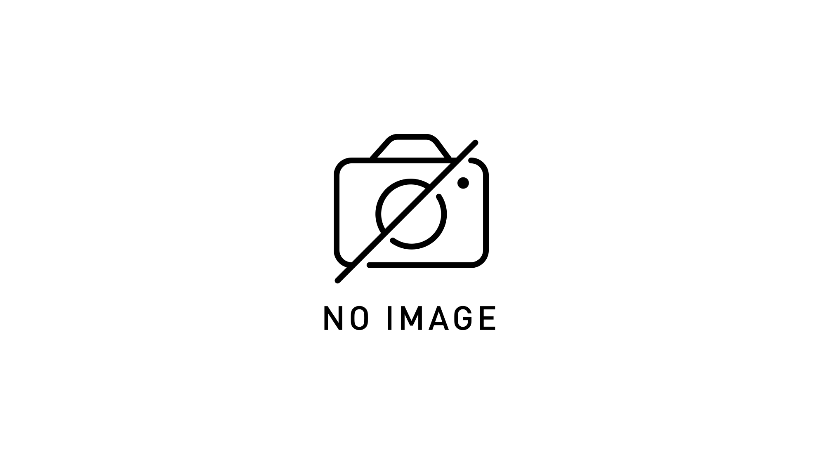
青原神楽社中
〒697-0212
島根県浜田市金城町
代表者:岡田 利広
詳細はこちら
【氏神神社名】---【団体の発足時期】---
【伝承されている神楽の区分】---
【保持演目】
穀種元・恵比須・塵輪・道がえし・天神・八幡・八衢・大蛇・熊襲・日本武尊・頼政・黒塚・塩祓い・鍾馗
【備考】---
【更新日】---
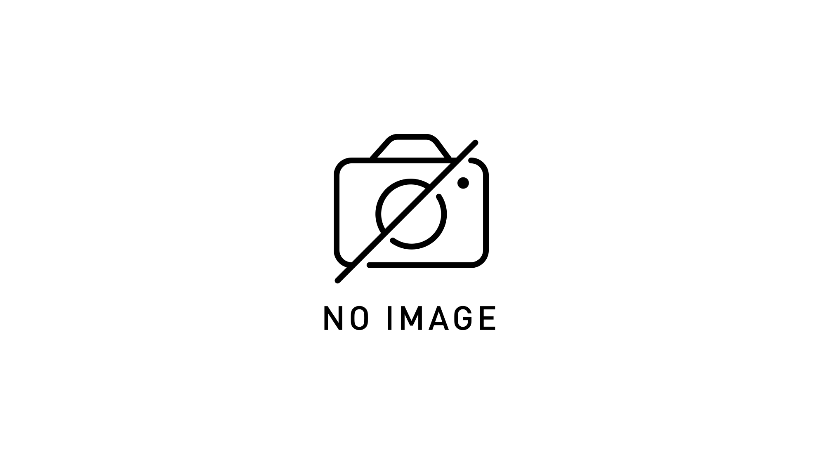
石見神楽 亀山社中
〒697-0062
島根県浜田市熱田町
代表者:小川 徹
詳細はこちら
【氏神神社名】---【団体の発足時期】平成11年7月
【伝承されている神楽の区分】八調子 石見神楽
【保持演目】
神楽・塩祓・神迎・四神・四剣・神祇太鼓・鍾馗・天蓋・八幡・塵輪・頼政・貴船・日本武尊・天神・八衢・五神・熊襲・岩戸・黒塚・大蛇・胴の口・恵比須・真榊・八十神・鈴神楽・鹿島・五条橋・かっ鼓・切目・道がへし・五穀種元・御座
【備考】
島根県西部に伝承される八調子石見神楽を継承し、発足当初から多くの神楽関係者の皆様、そして神楽ファンの皆様に支えられ活動してまいりました。この場をおかりしまして社中員一同厚く御礼申し上げます。これからも、神楽のみならず、神楽人としての生き方を真に見つめ、人となりを磨き、社中理念でもある「温故知新」の精神を貫き、敬神感をもとに伝統芸能を継承すべく、敬神礼法・儀式舞・能舞の習得伝承に社中員一丸となり精進する所存でございます。今後ともご指導ご鞭撻、ならびにご声援賜りますようお願い申し上げます。
【更新日】---
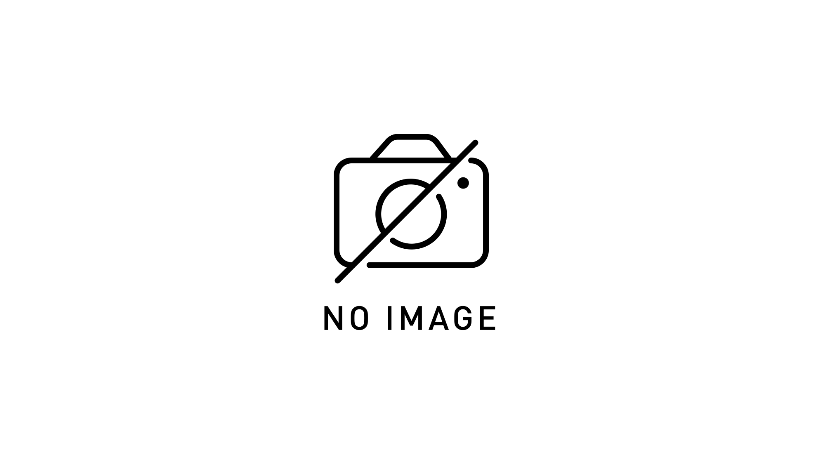
有福神楽保持者会
〒695-0101
島根県浜田市下有福町
代表者:佐々木 昌延
詳細はこちら
【氏神神社名】下有福八幡宮【団体の発足時期】江戸時代
【伝承されている神楽の区分】石見神楽
【保持演目】
<旧舞>鈴神楽・神迎え・神降し・神祇太鼓・帯舞・四神・四剣・諸太刀・御座舞・五穀種元・尊神・天蓋・榊舞・荒平・岩戸・恵比須・鹿島・かっ鼓・切目・貴船・熊襲・黒塚・五郎の王子・鐘馗・神武・人倫・関山・武ノ内・道がえし・天神・八幡・八十神・大蛇・日本武尊・頼政・大江山
<新舞>柿本人麻呂(作・40年くらい前)・鬼首岩(平成になってから)
【備考】
有福神楽は約300年の歴史があり、保持演目39演目あります。私達の町内は今現在80戸ぐらいの小さな集落です。その昔は3分の1にもみたない戸数と思われますが、よく今まで継承されてきたものだと改めて歴史を感じます。テンポの早い舞と有福神楽は刀の舞を特徴としています
【更新日】2006/5/3
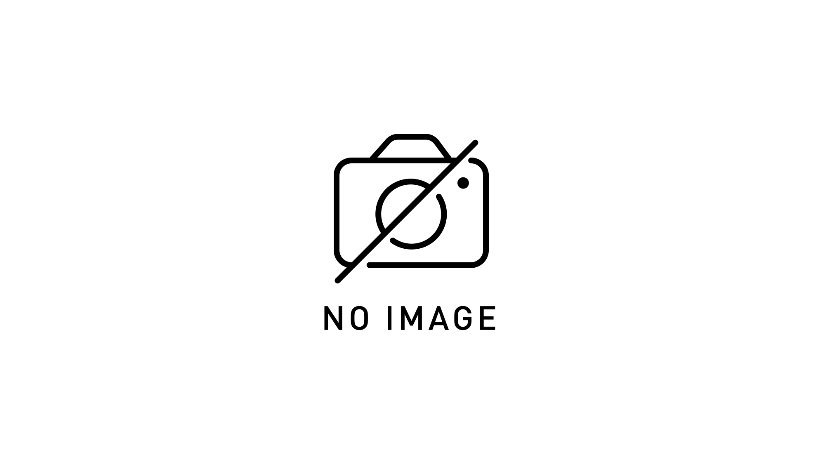
後野神楽社中
〒697-0011
島根県浜田市後野町
代表者:虫谷 昭則
詳細はこちら
【氏神神社名】---【団体の発足時期】---
【伝承されている神楽の区分】---
【保持演目】
鈴神楽・塩祓い・神迎え・神祇太鼓・五穀種元・天蓋・真榊・岩戸・恵比須・鹿島・かっ鼓・切目・黒塚・五神・鐘馗・塵輪・道がえし・天神・八幡・八衢・八十神・大蛇・日本武尊・頼政・大江山・鏡山
【備考】
現在の後野神楽社中は大正9年に結成された土井口神楽社中がその前身であります。
昭和48年に土井口地区の後継者不足から後野全町内の若手に呼びかけ、後野神楽社中として再発足しました。
【更新日】2006/2.7

宇津井神楽社中
〒697-0312
島根県浜田市宇津井町
代表者:平田 政敏
詳細はこちら
【氏神神社名】---【団体の発足時期】---
【伝承されている神楽の区分】---
【保持演目】---
【備考】---
【更新日】---
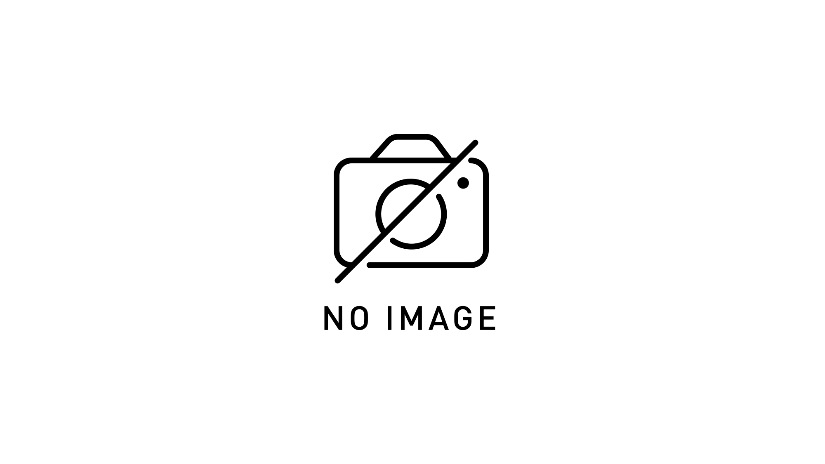
石見神楽 大尾谷社中
〒697-0062
島根県浜田市宇野町
代表者:河上 直道
詳細はこちら
【氏神神社名】---【団体の発足時期】---
【伝承されている神楽の区分】---
【保持演目】
鈴神楽・塩祓い・神迎え・神祇太鼓・五穀種元・天蓋・岩戸・恵比須・鹿島・かっ鼓・切目・熊襲・黒塚・五神・鐘馗・神武・塵輪・道がえし・天神・八幡・八十神・大蛇・日本武尊・頼政・大江山・橋弁慶
【備考】
我々大尾谷社中は、江戸次第末期に結成され当時は6調子にて演じられていました。その後昭和初期に8調子のリズムに変えられたと、伝えられております。
各社中の例大祭はもとより県内外の諸行事にも積極的に参加し、地元の郷土芸能をより多くの方々に知って頂ける様、日夜精進致しております。
【更新日】2006/2/7
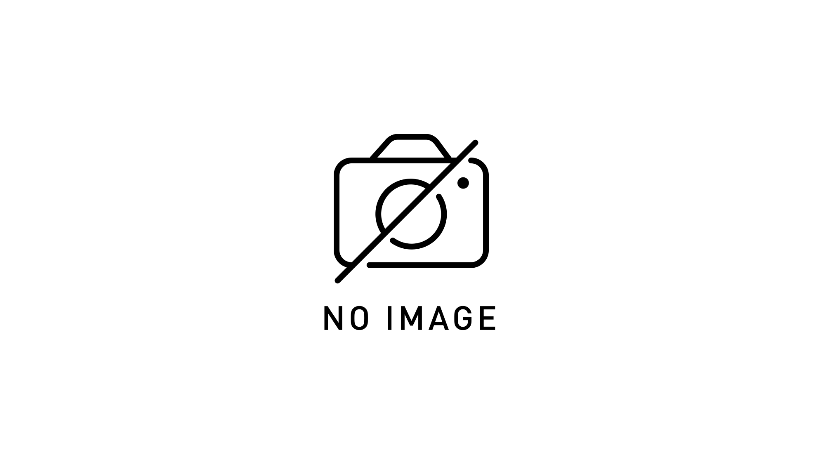
大尾谷子供神楽団
〒695-0102
島根県浜田市宇野町
代表者:坂本 壮護
詳細はこちら
【氏神神社名】若一王子神社【団体の発足時期】平成18年7月
【伝承されている神楽の区分】---
【保持演目】
鈴神楽、塩祓い、神迎え、八幡、恵比須、岩戸、道返し
【備考】大尾谷子供神楽団は、平成18年7月に大人の石見神楽大尾谷社中の指導の下、結成致しました。神楽の大好きな子供たちが集まり、現在(2024年)は小学3年生から中学3年生まで、11名の団員で日々練習に励んでおります。神楽活動を通じて将来を担う継承は勿論のこと、礼儀、挨拶、感謝の意を 養いつつ、子どもの育成に務めてまいります。
まだまだ演目数は少ないですが、郷土芸能石見神楽の継承に向け、精進してまいります。 今後ともご声援を宜しくお願いします。
【更新日】2024/12/25
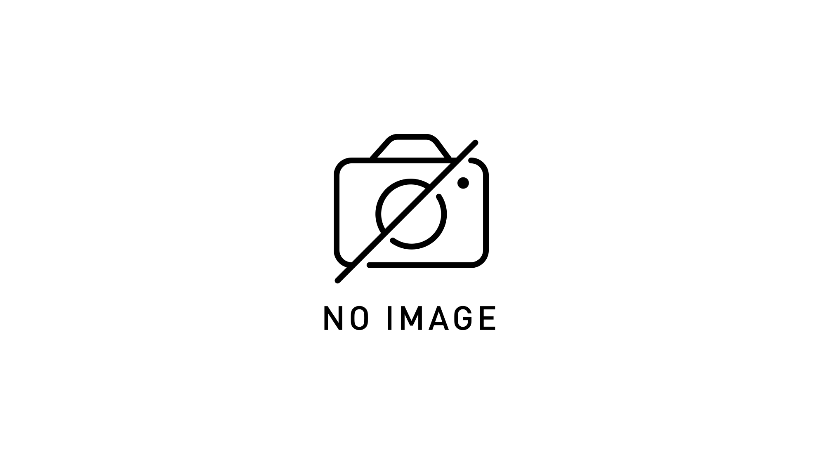
石見神代神楽 上府社中
〒697-0005
島根県浜田市上府町
代表者:岩川 清
詳細はこちら
【氏神神社名】郷社八幡宮【団体の発足時期】江戸時代 1806年
【伝承されている神楽の区分】八調子 石見神代神楽
【保持演目】
<旧舞>鈴神楽・塩祓・眞榊・神迎・八幡・神祇太鼓・かっ鼓・切目・道がへし・四神・四剣・鹿島・天蓋・塵輪・八十神・天神・黒塚・鐘馗・日本武尊・岩戸・恵比須・大蛇・五穀種元・頼政・八衢・五神(五郎の王子)
<新舞>大江山
【備考】
上府神楽社中は、文化3年頃より盛んになり、慶応年間に隠岐国奉納の記録も残されています。昭和45年、大阪万博「お祭り広場」に出演。世界の人に絶賛を博し、神楽ブームの源となりました。その後、全国商工会祭、お国自慢西東、ポートピア神戸国体、広島フラワーフェスティバル、うみしま博覧会、花と緑の博覧会、夢みなと博覧会などの国内のイベントに多数参加し、1999年は国民文化祭にも参加。中国、韓国、デンマーク、アメリカ・ジャパンウィーク、EUジャパンフェスタ、ペルーボリビア移住100周年、など海外でも高い評価を受けています。昭和47年の結成以来、芸、儀礼、挨拶などの勉強に励み、今まで150人もの人が巣立ち、郷土芸能保存に有効に役立っています。また、陰陽神楽大会で度々優勝し浜田八調子神楽を評価頂いています。
石州浜田太鼓 代表 岩川清
神祇太鼓(胴の口)を基本に伝統太鼓集団を結成し、今年で27年を経過しました。昭和60年に正式に石州浜田太鼓団として和太鼓の研究にあわせ、郷土の偉人を敬う「会津屋八右衛門」を発表し各地で絶賛を頂いています。今後も伝統芸能を固く継承保存に努め、さらに和太鼓を通じてふるさと発起し活動を展開しようと思います。
【更新日】2006/5/3
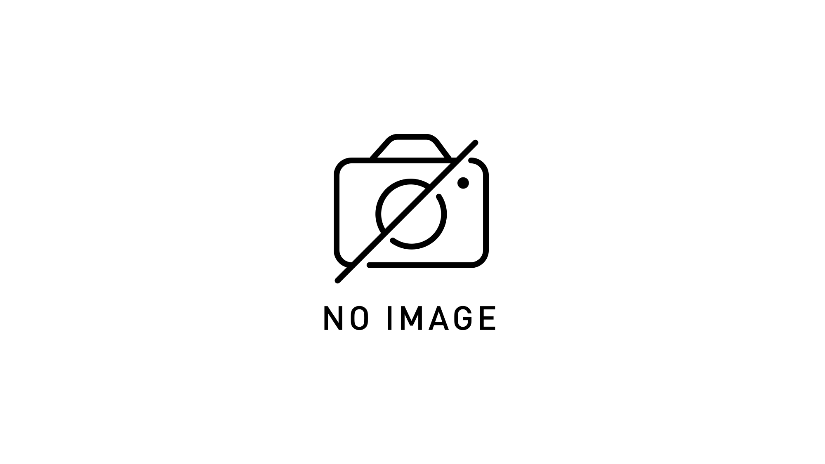
石見神楽 佐野神楽社中
〒697-0311
島根県浜田市佐野町
代表者:上岡 直晴
詳細はこちら
【氏神神社名】八旗山 佐野八幡宮【団体の発足時期】明治5年10月
【伝承されている神楽の区分】石見神楽
【保持演目】
<旧舞>大蛇・鐘馗・天神・武の内・塵輪・五神・大江山・日本武尊・黒塚・頼政(ほかに八調子神楽多演目)
<新舞>三上山・有明・天海
【備考】
明治4年の神職演舞禁止令により、氏子に引き継がれたとされており、六調子から勇壮華麗な八調子(大正6年)へと移行した。国内各地の神社奉納はもとより、科学万博、国民文化祭などにも出演し、また海外においてもアメリカ(ハリウッド)、台湾に単独出演。市合同社中ではアメリカ(シアトル・ソルトレイク・ニューヨーク)、中国、韓国、オーストラリアなどで演舞し、友好親善につとめながら、研鑚を重ね好評を得ている。
【更新日】2007/3/22
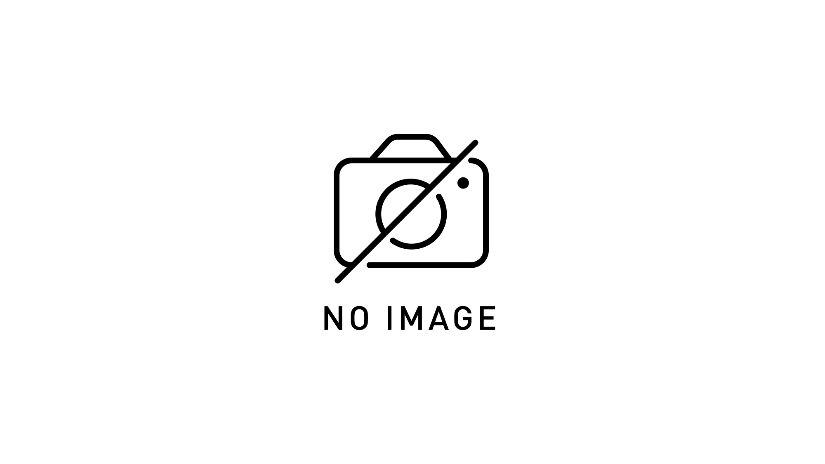
石見神楽 長澤社中
〒697-0002
島根県浜田市生湯町
代表者:長冨 幸男
詳細はこちら
【氏神神社名】長澤神社【団体の発足時期】明治5~6年
【伝承されている神楽の区分】石見神楽
【保持演目】
<旧舞>鈴神楽・塩祓・八幡・神祇太鼓・かっ鼓・切目・鹿島・天蓋・八十神・天神・黒塚・鐘馗・日本武命・岩戸・恵比須・八衢・五神・大蛇
<新舞>弁慶・加藤清正
【備考】---
【更新日】2006/5/3
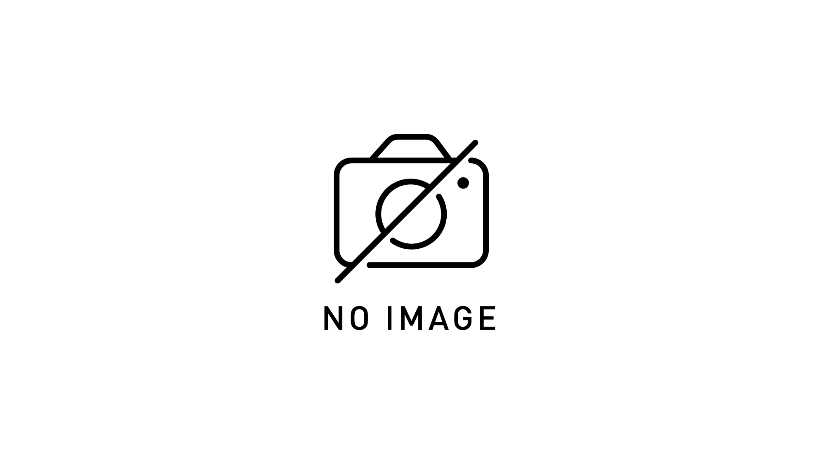
石見神楽 長浜社中
〒697-0062
島根県浜田市熱田町
代表者:安岡 一正
詳細はこちら
【氏神神社名】---【団体の発足時期】---
【伝承されている神楽の区分】---
【保持演目】
塩祓い・神迎え・神祇太鼓・四神・四剣・五穀種元・天蓋・真榊・岩戸・恵比須・鹿島・かっ鼓・切目・熊襲・黒塚・五神・鐘馗・塵輪・天神・八幡・八衢・八十神・大蛇・日本武尊
【備考】---
【更新日】2006.2.7
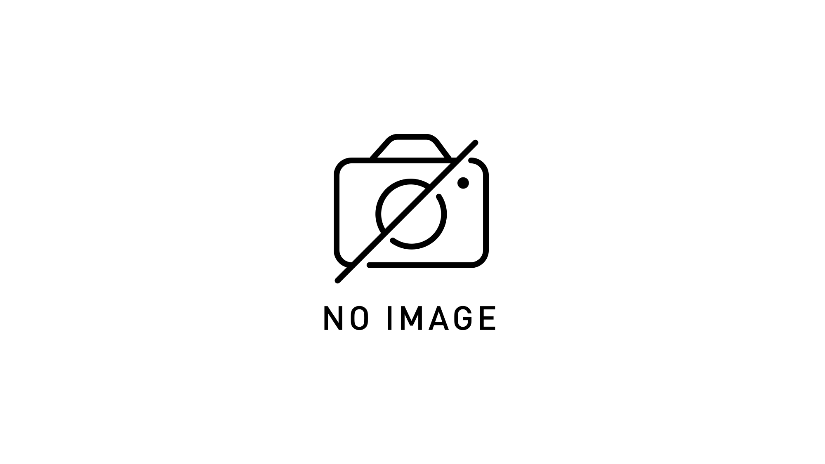
西村神楽社中
〒697-1337
島根県浜田市西村町
代表者:日高 均
詳細はこちら
【氏神神社名】---【団体の発足時期】---
【伝承されている神楽の区分】---
【保持演目】
鈴神楽・塩祓い・神迎え・神祇太鼓・四神・四剣・五穀種元・天蓋・岩戸・恵比須・鹿島・かっ鼓・切目・熊襲・黒塚・五神・鐘馗・塵輪・道がえし・天神・八幡・八衢・八十神・大蛇・日本武尊・頼政
<創作神楽>闇金大魔王
【備考】
石見神楽は、石見地方(島根県西部地域)に伝わる里神楽で、各地区毎の祭礼の際に夜を徹して演じられます。
演目の数は三十数演目に及び、その多くが日本書紀を題材としています。現在では、各種大会、婚礼のアトラクション等でも欠かすことのできない郷土の代表的な伝統芸能となっています。
中でも大蛇(おろち)は、三十数演目ある石見神楽の中の華と言われており、須佐之男の命(すさのおのみこと)の八岐の大蛇(やまたのおろち)退治を題材としたもので、八頭の大蛇がのたうちまわり、須佐之男の命との格闘シーンは、見る人を必ず感動させることでしょう。
石見神楽の起源は定かでは有りませんが、室町後期には演じられていたとも言われています。明治初期に石見の国学者たちによる神楽改正があり、それまでの六調子神楽と呼ばれる優雅でゆるやかなテンポの神楽から、勇壮で早いテンポの八調子神楽へと移行され浜田市を中心に伝承されています。
【更新日】2006/2/7
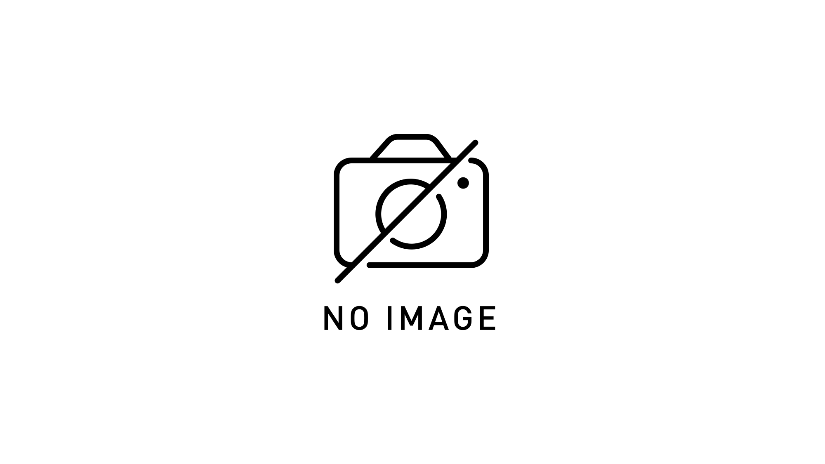
日脚神代神楽社中
〒697-1322
島根県浜田市日脚町
代表者:養庵 敏弘
詳細はこちら
【氏神神社名】日脚天上岡八幡宮【団体の発足時期】室町時代
【伝承されている神楽の区分】石見神楽
【保持演目】
神楽・塩祓・眞榊・帯舞・御蓙舞・神迎・八幡・神祇太鼓・双刀・かっ鼓・切目・道がえし・四神・四剣・鹿島・天蓋・塵輪・八十神・天神・黒塚・鐘馗・日本武尊・岩戸・恵比須・大蛇・五穀種元・八衢・熊襲・五神
【備考】
日脚神楽の源は、さだかではありませんが、記録などから寛政年間にはすでに盛んに活躍していたもと考えられます。そのころは、お宮に神仕えしている人たちが、社中をつくって神楽奉納していたものですが、明治になってからは、神楽は神職の手を離れて民間に移り、調子も悠長な六調子から現在の如き軽快な八調子へと変わっていきました。演技そのものも八調子に合致し、その勇壮優雅なることは他にないものと誇りに思っております。現在では保存後援会の尽力もあって、衣装等も一新され、ますます充実、活躍を続けております。この伝統ある神楽を後世に伝えるべく、日々研鑚尽力する所存であります。
【更新日】2006/5/3
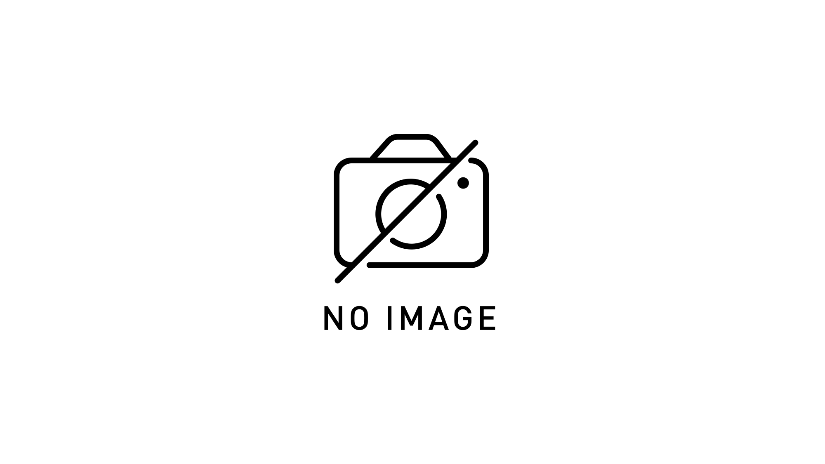
石見神楽 細谷社中
〒697-0013
島根県浜田市三階町
代表者:金岡 清
詳細はこちら
【氏神神社名】---【団体の発足時期】---
【伝承されている神楽の区分】---
【保持演目】
塩祓い・神迎え・天蓋・岩戸・恵比須・鹿島・熊襲・黒塚・鐘馗・塵輪・道がえし・天神・八幡・八十神・大蛇・日本武尊・頼政・かっ鼓・貴船・五条橋・神武
【備考】
細谷社中の歴史は、その起源を明確にすることは難しいが、天宝の初年には細谷の人は神楽を舞っていた事や、神官の反対を受けて罰せられていた事実が古書により明らかになっており、農民神楽の始祖社中であったと云っても過言ではなく、明治初期に故田中清見氏より指導を受け、新しい感覚を導入しながら石見地方の人情、風土に密着した社中として、石見神楽の歴史と歩みを共にした八調子石見神楽の源といえる社中である。
【更新日】 2006/2/7
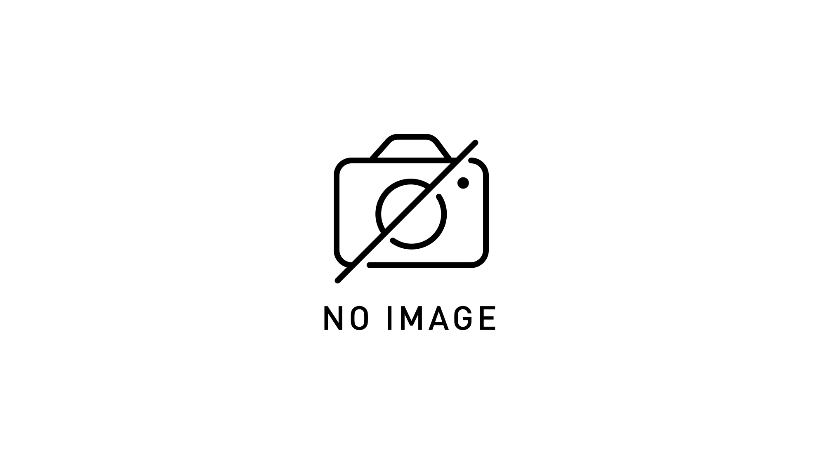
石見神楽 美川西神楽保存会
〒697-1332
島根県浜田市田橋町
代表者:浅浦 賢二
詳細はこちら
【氏神神社名】田橋大元神社【団体の発足時期】昭和42年4月
【伝承されている神楽の区分】石見神楽
【保持演目】
塩祓い・神祇太鼓・五穀種元・恵比須・熊襲・黒塚・五神・鐘馗・塵輪・道がえし・天神・八幡・八衢・大蛇・日本武尊・頼政
【備考】
私ども美川西神楽保存会は、明治初期に田橋舞子連中として発足、後に田橋神楽社中として活動していましたが、戦後団員不足により活動を休止していました。その後昭和42年に地元有志により活動を再開し、今日に至っています。
【更新日】2006/5/1
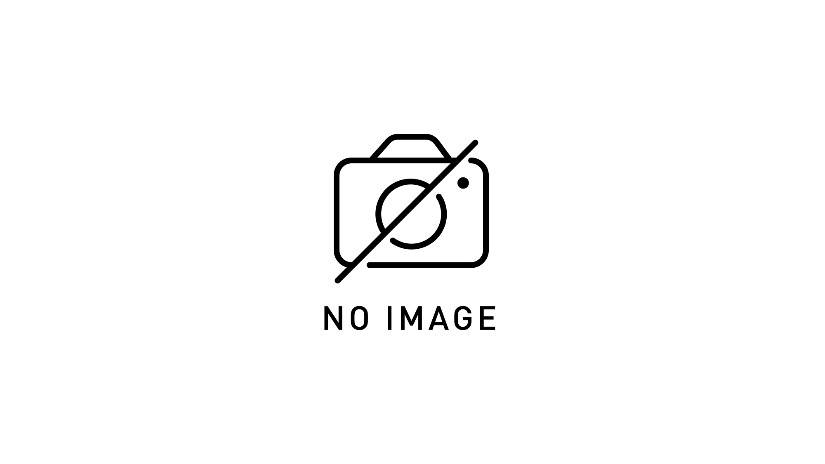
鍋石神楽社中
〒697-1333
島根県浜田市鍋石町
代表者:滝本 敏文
詳細はこちら
【氏神神社名】---【団体の発足時期】---
【伝承されている神楽の区分】---
【保持演目】---
【備考】---
【更新日】2006/2/7
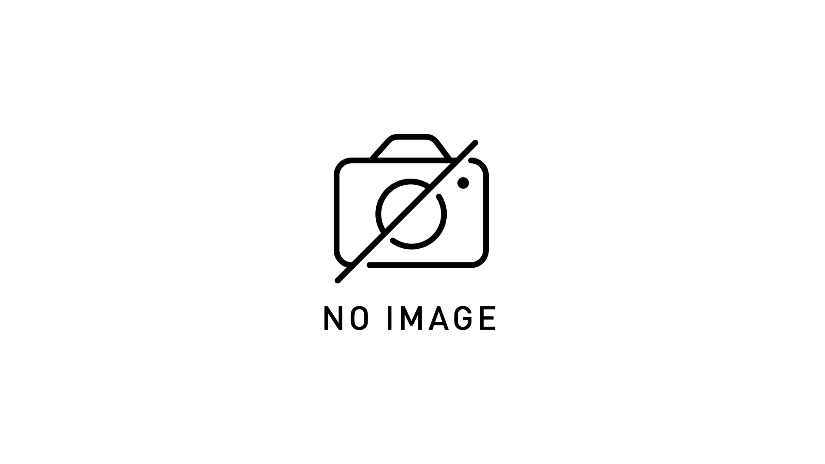
石見神楽 熱田保存会
〒697-0063
島根県浜田市長浜町
代表者:下本 泰明
詳細はこちら
【氏神神社名】---【団体の発足時期】---
【伝承されている神楽の区分】---
【保持演目】
神楽・塩祓い・恵比須・鐘馗・塵輪・道がえし・天神・八幡・大蛇・源三位頼政・かっ鼓・八衢・日本武尊・吟詮母・弁慶
【備考】2006/2/7
【更新日】---
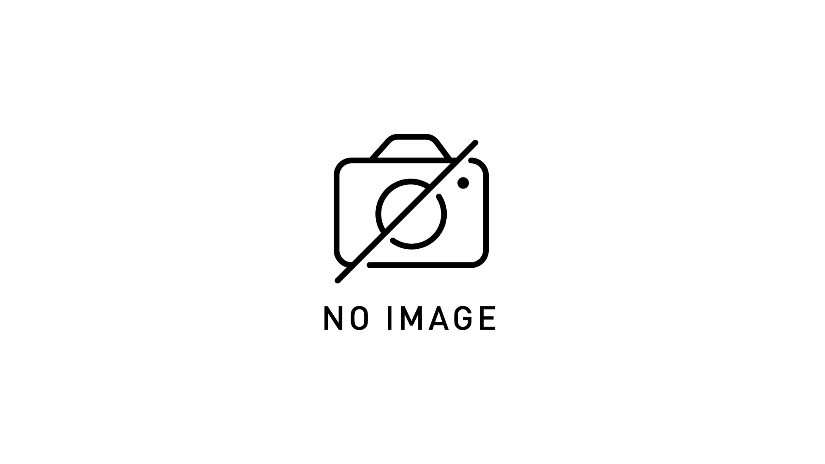
浜田市職員 石見神楽同好会
〒697-0027
島根県浜田市殿町1 浜田市役所内
代表者:飯田 賢夫
詳細はこちら
【氏神神社名】---【団体の発足時期】---
【伝承されている神楽の区分】---
【保持演目】
鈴神楽・塩祓い・神迎え・神祇太鼓・帯舞・四神・四剣・五穀種元・天蓋・真榊・岩戸・恵比須・鹿島・かっ鼓・切目・熊襲・黒塚・五郎の王子・鐘馗・塵輪・道がえし・天神・八幡・八衢・八十神・大蛇・日本武尊・頼政
【備考】---
【更新日】 2006/2/7
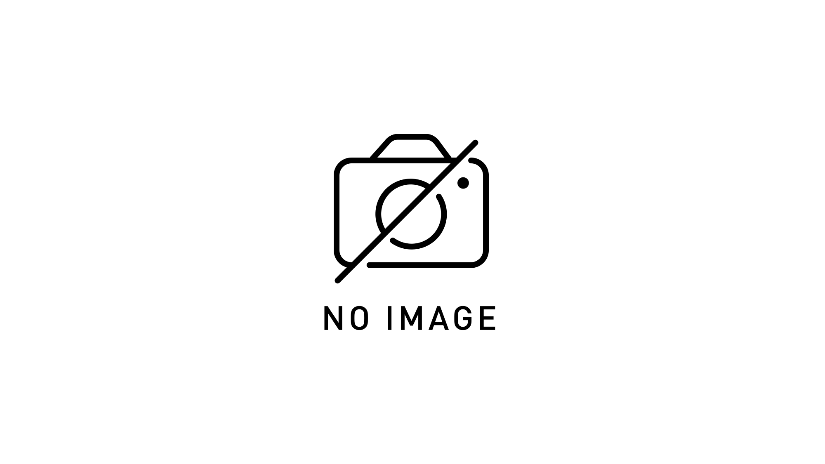
石見神楽周布青少年保存会
〒697-1326
島根県浜田市治和町
代表者:柴田 忠義
詳細はこちら
【氏神神社名】---【団体の発足時期】---
【伝承されている神楽の区分】---
【保持演目】
鈴神楽・塩祓い・神迎え・笛合唱・四神・岩戸・恵比須・鹿島・黒塚・五神・鐘馗・塵輪・道がえし・天神・八幡・天孫降臨・八十神・大蛇・(新)日本武尊・頼政
【備考】---
【更新日】 2007/5/21
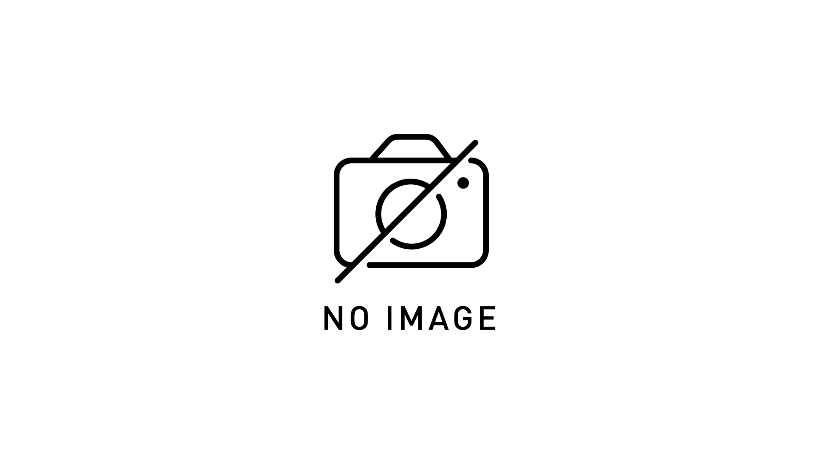
JR石見神楽同好会
〒697-0022
島根県浜田市浅井町
代表者:石飛 克之
詳細はこちら
【氏神神社名】---【団体の発足時期】---
【伝承されている神楽の区分】---
【保持演目】---
【備考】---
【更新日】2006/2/7

追原神楽社中
〒697-0301
島根県浜田市金城町
代表者:長山 一夫
詳細はこちら
【氏神神社名】---【団体の発足時期】---
【伝承されている神楽の区分】---
【保持演目】
鈴神楽・塩祓い・大蛇・頼政・鍾馗・塵輪・天神・八幡・恵比須武
【備考】---
【更新日】2016/01/19
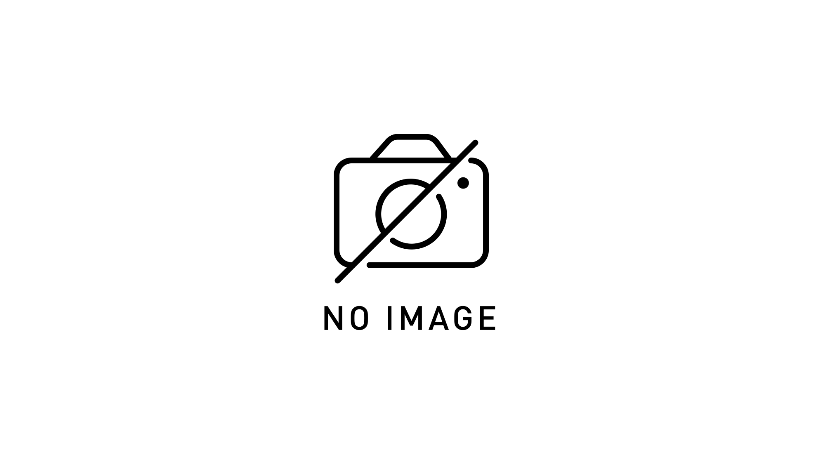
上内田神楽保存会
〒697-
島根県浜田市
代表者:
詳細はこちら
【氏神神社名】---【団体の発足時期】---
【伝承されている神楽の区分】---
【保持演目】---
【備考】---
【更新日】 2016/01/19
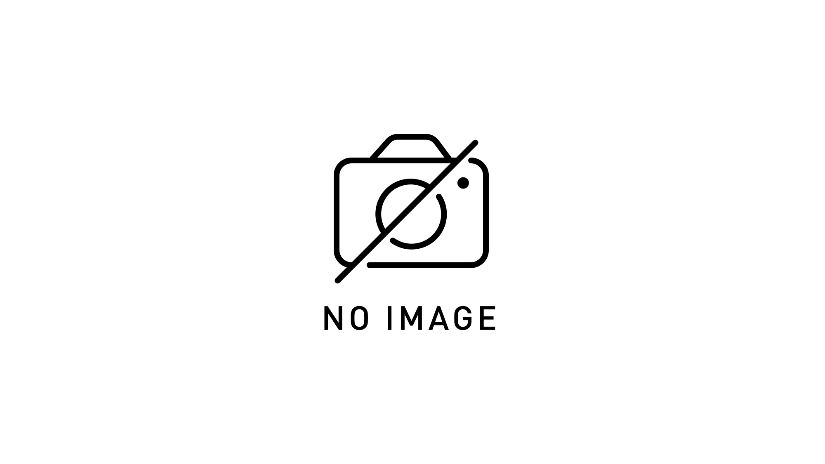
漁山神楽保存会
〒697-
島根県浜田市
代表者:小川 安夫
詳細はこちら
【氏神神社名】---【団体の発足時期】---
【伝承されている神楽の区分】---
【保持演目】---
【備考】---
【更新日】---
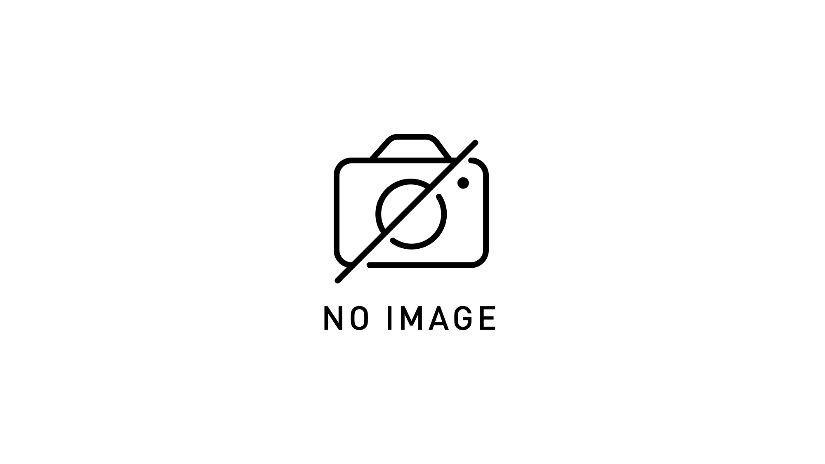
周布鶯巣神楽保存会
〒697-
島根県浜田市
代表者:川方 啓太郎
詳細はこちら
【氏神神社名】---【団体の発足時期】---
【伝承されている神楽の区分】---
【保持演目】
道がえし・恵比須・大蛇
【備考】---
【更新日】2016/01/19
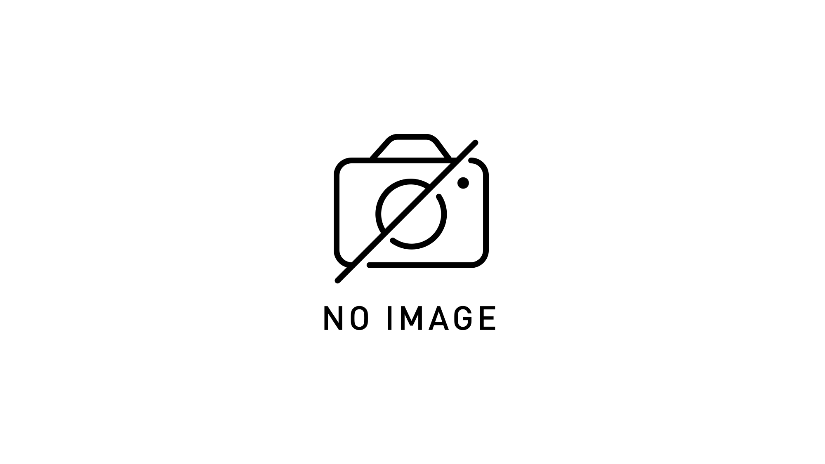
石見神楽 浅井社中
〒697-
島根県浜田市
代表者:川上 伸志
詳細はこちら
【氏神神社名】---【団体の発足時期】---
【伝承されている神楽の区分】---
【保持演目】
塵輪・黒塚・大蛇
【備考】---
【更新日】2024/12/26
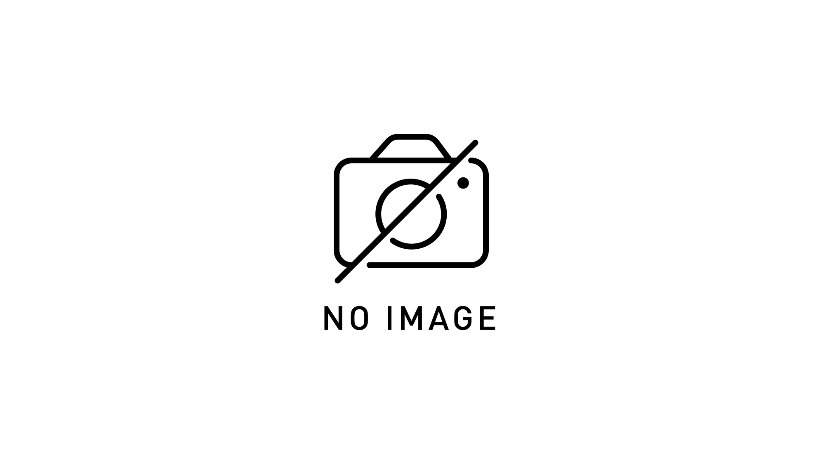
石見神楽 宇野社中
〒697-
島根県浜田市
代表者:佐々木 大輔
詳細はこちら
【氏神神社名】---【団体の発足時期】---
【伝承されている神楽の区分】八調子 石見神楽
【保持演目】
鈴神楽・塩祓い・榊葉・帯舞・神迎え・八幡・神祇太鼓・かっ鼓・切目・道がえし・四神・鹿島・天蓋・塵輪・八十神・天神・黒塚・鐘馗・日本武尊・岩戸・恵比須・大蛇・五穀種元・頼政・八衢・熊襲・御座舞
<創作神楽>丸原城
【備考】
宇野保存会は、 島根県浜田市宇野町にある、石見神楽を継承する団体です。
昭和初期には、「宇野社中」として市内で神楽を奉納していましたが、昭和15年の火災により衣裳や道具類を消失し、活動が途絶えていました。
その後は有志による地元での上演が何度か行われ、また、平成4年から平成10年頃にかけては、地元の子供たちが地区の行事などで神楽の上演を行っていました。しかし、少子化の波にのまれ、再び活動を休止することになってしまします。
平成15年、大人になったかつての教え子たちが「宇野神楽同好会」として団体を再結成しました。平成17年に「石見神楽宇野保存会」に名称を改め現在に至ります。
地元での上演・奉納はもちろんのこと、市内での公演や老人ホームの慰問なども積極的に行っています。
また、石見神楽を全国に知ってもらうべく、その足掛かりとして浜田市内にある県立大学の学生とも連携し、大学のサークルである「舞濱社中」の指導も行っています。
八調子の勢いのある舞を得意とし、昔ながらの素朴さが醸し出す芸の美しさ・深みを大切に、郷土芸能の継承に努めています。
【更新日】2016/01/19